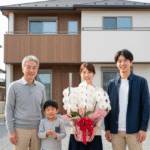新築の家が完成し、喜びもひとしおの時期、次に頭を悩ませるのがお披露目会ではないでしょうか。
特に、新築祝い 呼ぶ人をどこまでの範囲にするかは、多くの方が迷うポイントです。
親戚や友人、会社関係者など、誰を招待するべきか、また招待しない方へのマナーはどうすれば良いのか、考え始めるとキリがありません。
お披露目会を開催する適切な時期や、当日に向けた具体的な準備の流れも気になるところです。
また、お祝いをいただいたものの、どうしても招待できない方へのお返し、つまり内祝いの選び方やご祝儀の相場についても知っておきたいものです。
呼ばれた側としても、手土産に何を持っていけば喜ばれるのかは重要な関心事でしょう。
この記事では、そんな新築祝いにまつわる様々な疑問や不安を解消するために、呼ぶ人の範囲の決め方から、呼ばない場合の丁寧な対応、お披露目会の準備やマナーまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。
新居での新たなスタートを、素晴らしい人間関係とともに気持ちよく切れるよう、ぜひ参考にしてください。
fa-hand-pointer-o
この記事で分かる事、ポイント
- 新築お披露目会を開催するベストな時期
- お披露目会成功のための段取りと準備
- 招待客の範囲を決める際の基本的な考え方
- 親戚や友人、会社関係者など相手別の招待マナー
- お祝いを頂いたが招待しない方への丁寧な対応
- 失礼にならないお返しの品(内祝い)の選び方
- 訪問時に持参すると喜ばれる手土産の具体例
新築祝い 呼ぶ人の範囲はどこまで?お披露目会の基本マナー
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 新築お披露目会に最適な時期とタイミング
- 当日に向けての段取りとスムーズな準備
- 招待客の範囲を決める基本的な考え方
- 親戚や両親を招待する場合のポイント
- 親しい友人を招く際に気を付けたいこと
- 会社の上司や同僚を呼ぶ時のマナー
新築お披露目会に最適な時期とタイミング

新築の家が完成し、新しい生活が始まる喜びの中で、お世話になった方々へのお披露目会をいつ開催するかは、最初の重要な決断です。
最適な時期とタイミングを見極めることで、自分たちも落ち着いて準備ができ、ゲストにも心から楽しんでもらえます。
一般的に、新築お披露目会は引っ越しが完了してから1ヶ月から2ヶ月後が目安とされています。
なぜなら、この期間があれば、荷物の片付けがある程度進み、新しい家の生活リズムにも慣れてくるからです。
家具や家電がまだ揃っていなかったり、ダンボールが山積みになっていたりする状態では、せっかく来ていただくゲストに窮屈な思いをさせてしまうかもしれません。
まずは自分たちの生活基盤を整え、落ち着いてゲストをお迎えできる状態にすることが、何よりも大切なおもてなしと言えるでしょう。
また、季節を考慮するのも一つの方法です。
例えば、気候の良い春や秋は、ゲストが訪れやすく、庭やバルコニーがある家ならば、屋外のスペースも活用しやすいでしょう。
逆に、真夏や真冬、あるいは年末年始などの繁忙期は、ゲストの予定が立て込みやすいため、避けた方が無難かもしれません。
具体的な日程を決める際には、複数の候補日をリストアップし、特に招待したいと考えている主賓格の方々(例えば両親や特に親しい友人、お世話になった上司など)に、事前に都合を伺っておくとスムーズです。
全員の都合を合わせるのは難しいかもしれませんが、キーパーソンの予定を優先することで、より多くの方に喜んでもらえる会になります。
お披露目会は一度に全員を招く必要はありません。
親戚、友人、会社関係者など、関係性ごとにグループを分けて、複数回にわたって開催するのも賢明な方法です。
これにより、一回あたりのゲストの人数を抑えることができ、きめ細やかなおもてなしが可能になります。
例えば、「週末の昼間は親戚一同で和やかに」「平日の夜は会社の同僚とカジュアルに」といった形で、会の雰囲気や食事のメニューを変えることもでき、より満足度の高いお披露目会を実現できるでしょう。
当日に向けての段取りとスムーズな準備
新築お披露目会の日程が決まったら、次に行うべきは当日に向けた具体的な段取りと準備です。
計画的に進めることで、当日の慌ただしさを軽減し、心に余裕を持っておもてなしに集中できます。
まずは、招待客のリストアップから始めましょう。
誰を招くかを明確にし、連絡先を確認します。
リストが完成したら、次はお知らせの方法です。
正式な招待状を送るのも丁寧ですが、親しい間柄であれば電話やメール、SNSなどで連絡しても問題ありません。
その際には、日時、場所(新居の住所)、そしてもし会費制にする場合はその旨と金額を明確に伝えることが重要です。
出欠の返事は、準備の都合上、開催日の2週間前までにはもらうように設定しておくと良いでしょう。
次に考えるべきは、当日の食事や飲み物です。
招待するゲストの年齢層や好み、会の雰囲気(カジュアルかフォーマルか)に合わせてメニューを考えます。
すべて手作りするのは大変なので、デリバリーやケータリングサービス、あるいは持ち寄りのポットラックスタイルを取り入れるのも一つの手です。
飲み物は、アルコールを飲む人、飲まない人の両方に対応できるよう、ビールやワイン、日本酒などのアルコール類に加えて、お茶やジュース、ノンアルコール飲料も忘れずに用意しましょう。
家の掃除と整理整頓も欠かせない準備です。
特に、ゲストが使用する玄関、リビング、トイレ、洗面所は念入りに掃除しておきます。
新しい家を隅々まで見てもらいたい気持ちは分かりますが、プライベートな空間である寝室やクローゼットは、無理に見せる必要はありません。
見られたくない部屋はドアを閉めておき、「ここはプライベートな空間なので」と一言添えれば、ゲストも理解してくれるはずです。
また、意外と見落としがちなのが、ゲスト用のスリッパや、コートや手荷物を置く場所の確保です。
特に冬場は上着がかさばるので、クロークのように一時的に預かるスペースを用意しておくと、とてもスマートな印象を与えます。
車で来るゲストがいる場合は、駐車スペースの案内も必要です。
自宅の駐車場で足りない場合は、近隣のコインパーキングの場所を事前に調べておき、案内できるようにしておきましょう。
これらの準備をチェックリストにして管理すると、漏れがなくなり、よりスムーズに段取りを進めることができます。
招待客の範囲を決める基本的な考え方

新築祝い 呼ぶ人の範囲をどこまでにするか、これは多くの人が直面する最も悩ましい問題の一つです。
全員を招待できれば理想的ですが、家の広さや予算、おもてなしのキャパシティには限界があります。
無理をして大規模な会を開くよりも、自分たちが心からおもてなしできる範囲の人を招くことが、結果的に良いお披露目会につながります。
招待客の範囲を決める際の最も基本的な考え方は、「今後も末永く、親密なお付き合いを続けていきたい人」を優先することです。
まずは、両親や兄弟姉妹といった最も身近な家族、そして新築にあたって特にお世話になった親戚をリストアップするのが一般的です。
次に、学生時代の友人や会社の同僚など、プライベートで親しくしている人々を考えます。
ここでのポイントは、義理で招待するのではなく、心から「新しい家を見てほしい」と思える相手かどうかです。
家の購入に際して相談に乗ってくれた友人や、いつも気にかけてくれる会社の先輩など、感謝の気持ちを伝えたい相手を基準に選ぶと良いでしょう。
関係性によってグループを分けて考えるのも有効な方法です。
例えば、以下のように分類してみましょう。
- 親族(両親、兄弟姉妹、祖父母、特にお世話になった親戚)
- 親しい友人(学生時代の同級生、趣味の仲間など)
- 会社関係者(特にお世話になっている上司や同僚)
- ご近所の方々
このように分類した上で、どのグループまで招待するか、あるいはグループごとに別の機会を設けるかを検討します。
例えば、「親族だけのお披露目会」と「友人たちとのホームパーティー」を別々に開催すれば、それぞれの関係性に合った雰囲気でおもてなしができます。
会社の関係者を招く場合は、少しフォーマルな会になる可能性も考慮する必要があります。
ご近所の方々については、これから長いお付き合いになるため、良好な関係を築く意味で、簡単なご挨拶とともにお披露目会に招待するケースもありますが、これは地域の慣習や関係性の深さによります。
重要なのは、誰かを招待しなかったことが後の人間関係に悪影響を及ぼさないように配慮することです。
お祝いをいただいたにもかかわらず招待できなかった方へは、後日改めて内祝いをお贈りし、丁寧にお礼と事情を伝えることが不可欠です。
最終的には、夫婦でよく話し合い、二人にとって無理のない範囲で、感謝を伝えたい相手を招待するというスタンスが、後悔のない選択につながるでしょう。
親戚や両親を招待する場合のポイント
親戚や両親は、新築のプロセスを誰よりも温かく見守ってくれた存在です。
だからこそ、お披露目会に招待する際には、感謝の気持ちを込めて丁寧におもてなししたいものです。
身内だからといって甘えすぎず、いくつかのポイントを押さえることで、より喜んでもらえる会になります。
まず、招待するタイミングです。
両親や兄弟姉妹には、友人や会社関係者よりも先に、家の完成を報告し、お披露目の日程について相談するのが良いでしょう。
「まず最初に見てほしい」という気持ちを伝えることで、特別に思っていることが伝わります。
日程を決める際も、彼らの都合を最優先に考える姿勢が大切です。
当日のもてなしについては、リラックスした雰囲気の中にも、けじめを持たせることがポイントです。
食事は、手料理を振る舞うのも良いですが、準備が大変な場合は、少し豪華な仕出し弁当や、人気のレストランからテイクアウトを用意するのもおすすめです。
特に年配の親戚がいる場合は、食べ慣れた和食などが喜ばれる傾向にあります。
飲み物も、それぞれの好みを事前にリサーチしておくと、より心のこもったおもてなしができます。
家の案内をする際には、ただ部屋を見せるだけでなく、こだわったポイントや、家づくりのエピソードなどを交えながら話すと、会話が弾み、楽しい時間になります。
例えば、「このリビングの窓は、日当たりを一番に考えて設計したんです」とか、「キッチンの収納にはこだわって、こんな工夫をしました」といった具体的な話は、聞いている側も興味深く感じます。
また、親戚や両親からは高額な新築祝いをいただくことも少なくありません。
お披露目会でのおもてなしが、そのお返し(内祝い)を兼ねるという考え方もありますが、いただいた金額によっては、別途お返しの品物を用意するのがマナーです。
このあたりの判断は、家ごとの慣習や親との関係性にもよるので、事前に相談しておくと安心です。
他の招待客との関係性も考慮しましょう。
例えば、夫側の親戚と妻側の親戚を同時に招く場合は、両家が気まずい思いをしないように、席の配置を工夫したり、夫婦が間に入って会話の橋渡しをしたりする配慮が必要です。
もし、親戚と友人を一緒に招待する場合は、親戚を上座に案内するなど、礼儀をわきまえた対応を心がけましょう。
最も大切なのは、これまでの感謝と「これからもよろしくお願いします」という気持ちを伝えることです。
心のこもったおもてなしを通じて、新しい家でのスタートを家族みんなで祝福する、そんな温かい一日にしましょう。
親しい友人を招く際に気を付けたいこと

気心の知れた友人たちを新居に招くのは、非常に楽しく、心躍るイベントです。
しかし、親しい間柄だからこそ、つい配慮を忘れがちになることもあります。
友人たちに心から楽しんでもらい、自分たちも気疲れしないためには、いくつかのポイントに気を付けたいものです。
まず、友人たちに余計な気を使わせない雰囲気作りが大切です。
ご祝儀や手土産について、頭を悩ませる友人も少なくありません。
そこで、「お祝いは不要だから、気軽に遊びに来てね」と事前に一言伝えておくと、相手の負担を軽くすることができます。
もし会費制にする場合は、その旨と金額を明確に伝えましょう。
例えば、「一人3,000円でデリバリーを取ろうと思うんだけど、どうかな?」といったように、相談する形で伝えると、角が立ちません。
食事の準備も、あまりに気合を入れすぎると、かえって友人が恐縮してしまうことがあります。
手の込んだコース料理を用意するよりも、みんなでワイワイつまめるようなピザや唐揚げ、サラダなどを用意したり、いっそのこと「持ち寄りパーティー(ポットラック)」形式にしたりするのも楽しいでしょう。
その際は、食事系、デザート系など、持ち寄るもののジャンルが偏らないように、事前に軽く調整しておくとスムーズです。
子連れの友人がいる場合は、特に配慮が必要です。
子供が退屈しないように、おもちゃやDVDを用意しておくと喜ばれます。
また、子供が走り回って家具や壁に傷をつけたり、飲み物をこぼしてしまったりすることもあるかもしれません。
そうした事態を想定し、高価な調度品や壊れやすいものは、事前に片付けておくと、お互いに気兼ねなく過ごせます。
授乳やおむつ替えが必要な赤ちゃんがいる場合は、静かな個室を一つ提供できるように準備しておくと、非常に親切です。
友人関係のグループにも配慮しましょう。
学生時代のグループ、会社の同僚グループなど、共通の話題で盛り上がれるように、同じコミュニティの友人たちをまとめて招待するのが基本です。
もし、異なるグループの友人を一緒に招く場合は、お互いが孤立しないように、ホストである自分たちが積極的に間に入り、それぞれの友人を紹介して、会話のきっかけを作ってあげることが大切です。
最後に、お開きの時間です。
楽しい時間はあっという間に過ぎますが、あまりに長居になると、ホスト側も疲れてしまいますし、ゲスト側も帰り時を見失ってしまうことがあります。
最初に「今日は〇時くらいまで、ゆっくりしていってね」と、目安の時間を伝えておくと、お互いに気持ちよく会を終えることができます。
親しい友人との新築祝いは、堅苦しいマナーよりも、思いやりの心が何より大切です。
みんなが笑顔で過ごせるような、温かい空間作りを心がけましょう。
会社の上司や同僚を呼ぶ時のマナー
会社の上司や同僚を新築お披露目会に招待する場合は、親戚や友人とはまた違った配慮とマナーが求められます。
プライベートなイベントではありますが、会社の人間関係を意識した、節度ある対応を心がけることが重要です。
まず、誰を招待するかという範囲の選定は慎重に行いましょう。
直属の上司や、同じ部署の同僚など、仕事で密接に関わる範囲に留めるのが一般的です。
特定の人だけを招待すると、呼ばれなかった人が疎外感を覚えてしまう可能性もあるため、部署単位で声をかけるなどの配慮も時には必要です。
もし、招待するのが難しい場合は、「身内だけでささやかに行いますので」と伝え、後日、職場にお菓子などを持参して挨拶する形でも良いでしょう。
招待の仕方も丁寧に行う必要があります。
勤務時間中に個人的な話をするのは避け、休憩時間や就業後を見計らって、「この度、家を建てまして、もしご迷惑でなければ、ささやかなお披露目会にお越しいただけないでしょうか」と、謙虚な姿勢で声をかけます。
上司を招待する場合は、主賓としてお迎えする意識を持ちましょう。
日程も、相手の都合を最優先に調整するのがマナーです。
当日のもてなしについても、ビジネスマナーを少し意識すると良いでしょう。
上司が到着したら、まずは丁寧に迎え入れ、上座(リビングのソファなど、最も快適に過ごせる場所)へと案内します。
食事や飲み物を勧める際も、まずは上司からという順序を意識します。
会話の内容も、会社の愚痴や内部情報といったネガティブな話題は避け、当たり障りのない楽しい話題を心がけましょう。
家の案内についても、自慢話と受け取られないような配慮が必要です。
「奮発しました」といった表現よりも、「家族が快適に過ごせるように、この点だけはこだわりました」といった謙虚な伝え方の方が、好印象を与えます。
また、会社関係者を招待する場合、ご祝儀をいただくことがほとんどです。
お返し(内祝い)は不要という考えもありますが、感謝の気持ちとして、後日改めて品物をお贈りするのが丁寧な対応です。
あるいは、会費制にするという方法もあります。
その場合は、「皆様にお気遣いいただくのも恐縮ですので、会費制とさせていただけますでしょうか」と、低姿勢で相談するのがポイントです。
お開きの時間も、長くなりすぎないように配慮が必要です。
特に翌日が平日の場合は、相手の体調を気遣い、早めにお開きにするのがマナーです。
公私混同と捉えられないよう、節度と感謝の気持ちを持って接することが、会社関係者との良好な関係を保ちながら、お披露目会を成功させる鍵となります。
新築祝い 呼ぶ人を限定したい時や呼ばれた際のマナー
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- お祝いを頂いたが呼ばない人への対応
- 招待しない場合の失礼にならないお返しの選び方
- 訪問時に喜ばれる手土産のアイデア
- 【まとめ】後悔しない新築祝い 呼ぶ人のための判断基準
お祝いを頂いたが呼ばない人への対応

新築祝いをいただいたすべての人をお披露目会に招待できれば良いのですが、家の広さや準備の都合上、どうしても呼ぶ人を限定せざるを得ない場合があります。
そんな時、お祝いをくださったにもかかわらず招待しない方へ、どのように対応すれば失礼にあたらないのでしょうか。
最も重要なのは、感謝の気持ちを迅速かつ丁寧に伝えることです。
お祝いをいただいたら、まずは2〜3日以内、遅くとも1週間以内には電話や手紙でお礼の連絡を入れましょう。
メールやSNSでの連絡は、相手との関係性によっては問題ありませんが、目上の方や儀礼を重んじる方へは、電話か直筆のお礼状が最も丁寧な方法です。
その際に、お披露目会に招待できないお詫びも伝える必要があります。
しかし、その理由を詳細に説明する必要はありません。
「遠方でご足労をおかけするのも申し訳ないので」「身内だけでささやかに行うことになりまして」といったように、相手を気遣う言葉や、簡潔な理由を添えるだけで十分です。
下手に言い訳がましくなると、かえって不誠実な印象を与えかねません。
次に、お礼の気持ちを形で示す「内祝い」を贈ります。
内祝いは、いただいたお祝いへのお返しであり、お披露目会に招待しない場合は、この内祝いが感謝を伝える重要な役割を果たします。
贈るタイミングは、お祝いをいただいてから1ヶ月以内が目安です。
品物には、紅白の蝶結びの水引がかかったのし紙をつけ、表書きは「内祝」、その下に新しい姓を記載します。
品物を選ぶ際は、相手の好みや家族構成を考慮することが大切です。
自分たちの都合で招待できなかったというお詫びの気持ちも込めて、心を込めて選びましょう。
内祝いの品物には、必ずお礼状を添えるようにします。
お礼状には、いただいたお祝いへの感謝、新しい家での生活の様子、そしてお披露目会に招待できなかったことへのお詫びと、その理由を改めて簡潔に記します。
そして、「近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください」という一文を添えることで、相手を大切に思っている気持ちが伝わり、今後の良好な関係を維持することができます。
大切なのは、形式的な対応で終わらせるのではなく、「お祝いしてくれてありがとう」「招待できなくてごめんなさい」という誠実な気持ちを、言葉と品物で伝えることです。
その心がけがあれば、たとえお披露目会に招待できなくても、相手との関係がこじれることはないでしょう。
招待しない場合の失礼にならないお返しの選び方
お披露目会に招待しない方へ贈る内祝いは、感謝とお詫びの気持ちを伝える大切な贈り物です。
品物選びに失敗すると、せっかくの気持ちが伝わらないばかりか、かえって失礼にあたる可能性もあります。
ここでは、相手に喜ばれ、かつ失礼にならないお返しの選び方について、具体的なポイントを解説します。
まず基本となるのが、内祝いの金額相場です。
一般的に、いただいたお祝いの品の金額、あるいはご祝儀の半額(半返し)から3分の1程度が目安とされています。
あまりに高額なものをお返しすると、かえって相手に気を使わせてしまうため、相場を守ることが大切です。
いただいた品物の値段がわからない場合は、インターネットなどでおおよその価格を調べてみましょう。
品物選びで最も無難で喜ばれるのは、いわゆる「消え物」です。
お菓子やコーヒー、紅茶、調味料、洗剤といった消耗品は、相手の趣味に左右されにくく、保管場所にも困らないため、多くの方に受け入れられやすい選択肢です。
選ぶ際には、少し高級感のあるブランドのものや、自分ではなかなか買わないような、こだわりのある品を選ぶと、特別感が伝わります。
また、タオルや食器用洗剤などの日用品も実用的で人気があります。
タオルを選ぶなら、質の良い今治タオルなど、使い心地の良いものを選ぶと喜ばれるでしょう。
相手の好みがわからない場合や、何を贈ればよいか迷ってしまう場合には、カタログギフトが非常に便利です。
カタログギフトなら、相手が本当に欲しいものを自分で選べるため、失敗がありません。
最近では、グルメ専門のカタログや、特定のブランドだけを集めたカタログなど、種類も豊富なので、相手のライフスタイルに合わせて選ぶことができます。
一方で、避けた方が良い品物もあります。
例えば、刃物(縁が切れることを連想させる)、ハンカチ(手巾(てぎれ)と書き、別れを意味する)、現金や金券(目上の方へは失礼にあたる)などが挙げられます。
また、相手のインテリアの趣味に合わない置物や、サイズのわからない衣類なども避けた方が無難です。
品物選びで最も大切なのは、相手のことを思いやる心です。
「この人は甘いものが好きだから、有名なパティスリーのお菓子にしよう」「お子さんがいるから、家族みんなで楽しめるジュースの詰め合わせが良いかな」というように、相手の顔を思い浮かべながら選んだ品物は、きっとその気持ちが伝わるはずです。
感謝とお詫びの気持ちを込めた丁寧なお礼状を添えて、心のこもった内祝いを贈りましょう。
訪問時に喜ばれる手土産のアイデア

新築のお披露目会に招待された際、悩むのが手土産です。
「お祝いは済ませているけれど、手ぶらで行くのも気が引ける…」と感じる方は多いでしょう。
心のこもった手土産は、お祝いの気持ちをさらに伝え、場の雰囲気を和ませる効果もあります。
ここでは、ホストに喜ばれる手土産のアイデアをいくつかご紹介します。
手土産選びの基本的な考え方は、「ホストの負担にならず、その場で消費できるもの」または「新生活に役立つ、いくつあっても困らない実用的なもの」です。</
まず、最も定番で喜ばれるのが、少し高級なお菓子やケーキです。
お披露目会のデザートとしてその場でみんなで楽しむことができますし、ホストが食事の準備をしている場合、デザートまで手が回らないこともあるため、非常に助かります。
日持ちのする焼き菓子の詰め合わせであれば、もしその場で食べきれなくても、後日ゆっくり楽しんでもらえます。
飲み物も人気の高い手土産です。
お酒が好きなホストであれば、少し珍しいクラフトビールや、出身地の地酒、食事に合わせやすいワインなどが喜ばれます。
お酒を飲まない家庭であれば、こだわりのコーヒー豆や紅茶のセット、質の良い果汁100%ジュースなどが良いでしょう。
子どもがいる家庭なら、子ども向けのジュースも忘れずに。
新生活に彩りを添える贈り物として、お花や観葉植物も素敵です。
ただし、大きな花束は花瓶の用意などホストに手間をかけさせてしまう可能性があるため、すぐに飾れるアレンジメントフラワーや、手入れが簡単な小さな観葉植物がおすすめです。
特に、お祝いのシーンにふさわしい華やかさと品格を兼ね備えた胡蝶蘭は、新築祝いの贈り物として大変人気があります。
「幸福が飛んでくる」という花言葉も、新しい門出にぴったりです。
最近では、通販で手軽に品質の良い胡蝶蘭を贈ることもでき、事前に相手の住所へ配送しておけば、当日の荷物にもならずスマートです。
実用的なアイテムとしては、上質なタオルや、おしゃれなデザインのキッチン雑貨(スポンジやふきんなど)、香りの良いハンドソープなども良いでしょう。
これらは消耗品であり、いくつあっても困らないため、気軽に受け取ってもらえます。
逆に、避けた方が良いのは、インテリアの趣味が分かれる置物や絵画、大きな家具などです。
また、火事を連想させるキャンドルやアロマグッズ、灰皿なども、新築祝いの手土産としては避けるのが一般的です。
手土産の相場は、3,000円から5,000円程度が一般的ですが、相手との関係性によって調整しましょう。
大切なのは金額よりも「おめでとう」の気持ちです。
相手の顔を思い浮かべながら、心を込めて選んだ手土産で、お祝いの気持ちを伝えましょう。
【まとめ】後悔しない新築祝い 呼ぶ人のための判断基準
新築祝いに誰を呼ぶか、そしてどのように対応するかは、新しい家での人間関係をスムーズにスタートさせるための重要なステップです。
これまで見てきたように、招待客の範囲決定から、お披露目会の準備、招待しない方への配慮、そして訪問する際のマナーまで、考えるべきことは多岐にわたります。
最後に、後悔しない選択をするための判断基準をまとめておきましょう。
まず、新築祝い 呼ぶ人を決める大原則は、「自分たちが無理なく、心からおもてなしできる範囲」にすることです。
見栄や義理で招待客を増やしすぎると、準備や当日の対応に追われ、ホスト自身が疲弊してしまいます。
それでは、せっかくのお祝いムードも台無しです。
「今後も親しく付き合っていきたい」「新しい家を心から見てほしい」と思える相手かどうかを、夫婦でじっくり話し合って決めることが最も大切です。
関係性に応じて、親戚、友人、会社関係者とグループを分け、それぞれに合ったタイミングや形式でお披露目会を開催するのも、賢明な判断と言えるでしょう。
次いで重要なのが、呼ばない人への配慮です。
お祝いをいただいたにもかかわらず招待できなかった方へは、感謝の気持ちを迅速に伝え、丁寧な内祝いを贈ることが不可欠です。
このフォローを怠ると、後の人間関係に溝が生まれてしまう可能性もあります。
「招待できず申し訳ない」という気持ちを誠実に伝えることで、相手もきっと理解してくれるはずです。
そして、お祝いの気持ちを伝える方法は、お披露目会への招待だけではありません。
心のこもった贈り物も、非常に有効なコミュニケーション手段です。
例えば、お祝いをいただいたけれど呼べなかった方への内祝いや、お披露目会に持参する手土産として、新しい門出を祝うにふさわしい品を選ぶことが大切です。
特に、胡蝶蘭のような華やかで縁起の良い贈り物は、お祝いの気持ちを格調高く伝えてくれます。
「幸福が飛んでくる」という花言葉を持つ胡蝶蘭は、まさに新生活のスタートに最適です。
最近では、高品質な胡蝶蘭を扱う通販サイトも多く、手軽に注文できるだけでなく、ラッピングやメッセージカードのサービスも充実しているため、心のこもったギフトを簡単に贈ることができます。
新築という人生の大きな節目を、誰と、どのように祝うか。
その一つひとつの判断が、これからの新しい生活をより豊かで幸せなものにしてくれます。
感謝と思いやりの心を忘れずに、自分たちらしい最高のスタートを切ってください。
fa-file-powerpoint-o
この記事のまとめ
- 新築祝いに呼ぶ人は「今後も親しくしたい人」を基準に選ぶ
- 無理のない範囲でおもてなしできる人数に絞ることが大切
- お披露目会は引っ越し後1〜2ヶ月の落ち着いた時期が最適
- 親戚・友人・会社関係者などグループ分けでの開催も有効
- 招待しない方へは迅速なお礼と丁寧な内祝いが不可欠
- 内祝いの相場は頂いたお祝いの半額から3分の1程度
- 内祝いには感謝と事情を伝えるお礼状を必ず添える
- 訪問時の手土産は消え物や実用的なものが喜ばれる
- 新築祝いの手土産として胡蝶蘭は華やかで縁起が良く人気
- 胡蝶蘭の花言葉「幸福が飛んでくる」は新たな門出に最適
- 会社関係者を招く際は節度とマナーを特に意識する
- 子連れのゲストにはおもちゃや安全面での配慮を忘れない
- 準備はチェックリストを作成すると段取りがスムーズになる
- 感謝と思いやりの心が最も重要なマナーといえる
- お祝いの気持ちを伝える贈り物には通販の胡蝶蘭が便利で確実