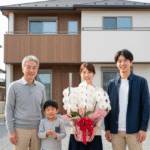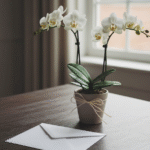この度は、大切な方の栄誉あるご就任、誠におめでとうございます。
そして、その輝かしい門出を祝う会で、就任祝い 司会という大役を任されたあなた様も、緊張と期待が入り混じった気持ちでいらっしゃることでしょう。
「司会なんて経験がないのに、どうしよう」「失敗したら主役に申し訳ない」といった不安から、進行や台本の準備、適切な挨拶の言葉選び、さらには当日の服装マナーに至るまで、様々な情報を探しているのではないでしょうか。
特に、祝辞の述べ方や、気の利いたプレゼント選びは、お祝いの気持ちを伝える上で非常に重要です。
この記事では、そのようなお悩みを抱える皆様のために、就任祝いの司会を成功させるための全ての情報を網羅的に解説します。
司会者の心構えから、具体的な台本の例文、さらにはお祝いの席に華を添える贈り物として最適な胡蝶蘭の紹介まで、これさえ読めば自信を持って当日に臨める、という内容を目指しました。
本記事で紹介するポイントや注意点を一つひとつ確認し、万全の準備を整えることで、あなたの司会はきっと、主役の新たなスタートを彩る素晴らしいものになるはずです。
fa-hand-pointer-o
この記事で分かる事、ポイント
- 就任祝いの司会者に求められる役割と心構え
- 当日スムーズに進行するための台本の作り方とポイント
- 失敗しないための服装マナーと身だしなみの注意点
- 心に響くお祝いの挨拶と祝辞を述べるコツ
- お祝いのプレゼントとして胡蝶蘭が選ばれる理由
- 開会から閉会まで使える司会進行の具体的な例文
- 就任祝いの場で避けるべき忌み言葉の知識
就任祝いの司会を成功に導く進行と準備の全知識
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 司会者に求められる役割と心構え
- スムーズな進行を実現する台本の作り方
- 当日の服装で気を付けたいマナーと注意点
- 心に響くお祝いの挨拶と祝辞のポイント
- 就任祝いのプレゼントには胡蝶蘭が最適
司会者に求められる役割と心構え

就任祝いの司会という大役を任されたとき、まず理解しておくべきことは、司会者の役割が単にプログラムを読み上げることだけではないという点です。
司会者は、その祝賀会の「演出家」であり「指揮者」です。
会の雰囲気を作り、時間通りに円滑に進行させ、主役である就任者を輝かせ、そして参加者全員が心からお祝いできる空間を作り出すことが最も重要な任務と言えるでしょう。
そのためには、いくつかの心構えが必要になります。
第一に、主役への敬意と祝福の気持ちを常に忘れないことです。
あなたの言葉遣いや立ち居振る舞い一つひとつが、会の品格を決定づけます。
主役のこれまでの功績や人柄を事前にリサーチし、尊敬の念を持って紹介することで、参加者の共感も深まるでしょう。
第二に、時間管理の徹底です。
祝賀会は、来賓の挨拶や余興など、多くのプログラムが組まれています。
開始時間や終了時間が決まっている中で、各プログラムの持ち時間を把握し、全体の流れをコントロールする能力が求められます。
時には、挨拶が長引いてしまった場合に、さりげなく次のプログラムへ促すといった機転も必要になるかもしれません。
第三の心構えは、常に会場全体に気を配ることです。
参加者の表情や反応、会場の音響や照明、食事の進捗状況など、あらゆる要素にアンテナを張り巡らせましょう。
例えば、会場が少し静かになってきたら、明るいトーンで話しかけて場を盛り上げる、逆に盛り上がりすぎている場合は、少し落ち着いた声で進行するなど、臨機応変な対応が場の雰囲気を良くします。
第四に、予期せぬトラブルにも冷静に対応する覚悟を持つことです。
マイクの不調、予定していた登壇者が来ない、進行が大幅に遅れるなど、イベントにトラブルはつきものです。
そんな時でも慌てず、笑顔を絶やさず、落ち着いて対処する姿勢が、参加者に安心感を与えます。
そのためにも、事前に起こりうるトラブルを想定し、対応策を考えておくと心に余裕が生まれます。
最後に、司会者自身がその場を楽しむことです。
司会者が緊張でこわばった表情をしていては、会場全体の雰囲気も硬くなってしまいます。
「主役の輝かしい門出を、皆さんと一緒にお祝いできることを嬉しく思う」という気持ちで臨めば、そのポジティブな感情は自然と声のトーンや表情に表れ、参加者にも伝わるものです。
これらの役割と心構えを胸に刻み、万全の準備を行えば、たとえ司会の経験が少なくとも、必ずや素晴らしい就任祝いの会を演出できるでしょう。
スムーズな進行を実現する台本の作り方
就任祝いの司会を成功させるための最も重要なツールが「台本」です。
台本は、司会者にとっての羅針盤であり、自信を持って当日を迎えるためのお守りのような存在になります。
アドリブに自信がある方でも、基本的な流れを記した台本を用意しておくことで、万が一の事態にも落ち着いて対応できるでしょう。
ここでは、スムーズな進行を実現するための台本作りのステップとポイントを具体的に解説します。
ステップ1:祝賀会の基本情報を整理する
まずは、会の骨格となる基本情報を正確に把握し、整理することから始めます。
以下の項目をリストアップしてみましょう。
- 会の正式名称
- 開催日時と場所
- 主役(就任者)の氏名、役職、経歴、人柄が分かるエピソードなど
- 主催者の氏名、役職
- 来賓の氏名、役職(特に祝辞を述べる方)
- 会の目的と雰囲気(厳粛な式典か、和やかなパーティーか)
- 全体の所要時間(開会から閉会まで)
特に主役に関する情報は、単なる経歴だけでなく、趣味や好きなこと、尊敬する点などのパーソナルな情報を集めておくと、紹介コメントに深みが出て、より温かみのある司会になります。
ステップ2:プログラムの順序と時間配分を決める
次に、当日のプログラム(式次第)を時系列に並べ、それぞれの所要時間を設定します。
これにより、全体の時間管理がしやすくなります。
一般的な就任披露パーティーの進行例は以下の通りです。
- 開会の辞
- 主催者挨拶
- 来賓祝辞
- 就任者(主役)挨拶
- 乾杯
- 歓談・食事
- 余興・イベント(任意)
- お祝いの電報(祝電)披露
- 閉会の辞
各プログラムの間に、司会者が話す時間を考慮に入れることも忘れないでください。
例えば、来賓祝辞が2名続く場合、1人目が終わった後、司会者が感謝を述べ、2人目を紹介するという流れになります。
この時間配分が、台本全体の設計図となります。
ステップ3:具体的なセリフを書き出す
全体の流れが決まったら、いよいよ具体的なセリフを書き出していきます。
この時、単に「開会の辞」と書くだけでなく、実際に口に出す言葉をそのまま文章にすることがポイントです。
「ただいまより、株式会社〇〇、新社長〇〇様のご就任を祝します祝賀会を、開会いたします」のように、一言一句書き起こしましょう。
特に重要なのが、人の名前や役職、会社名です。
絶対に間違えてはならない部分ですので、ふりがなを振るなどして、正確に読めるように準備してください。
また、セリフだけでなく、その時の自分の動き(「ここで一礼」「登壇者を拍手で迎える」など)や、音響・照明のきっかけなどもメモしておくと、当日慌てることがありません。
台本作りのポイント
読みやすい台本にするためには、いくつかの工夫があります。
まず、フォントは大きめにし、行間を十分に空けること。
緊張していると、小さな文字は読みにくくなります。
次に、ページをめくりやすいように、クリアファイルやバインダーに挟むと良いでしょう。
バラバラの紙のままでは、落としたり順番が分からなくなったりする可能性があります。
そして、完成した台本は、必ず声に出して読んで練習することです。
黙読するだけでは、言い間違いやすい箇所や、リズムが悪い部分に気づきにくいものです。
時間を計りながら練習すれば、時間配分の感覚も掴めます。
完璧な台本を作成することが、就任祝いの司会を成功に導く最大の鍵となるのです。
当日の服装で気を付けたいマナーと注意点

就任祝いの司会者は、会の「顔」ともいえる存在です。
そのため、服装は非常に重要であり、会の格式や雰囲気に合わせつつ、主役を引き立てるような品格のある装いが求められます。
ここでは、男性司会者、女性司会者それぞれについて、基本的な服装マナーと注意点を解説します。
男性司会者の服装マナー
男性の場合、基本的にはフォーマルなスーツスタイルが望ましいです。
色の選び方が最初のポイントになります。
最も無難で品格があるのは、ダークスーツです。
濃紺やチャコールグレーの無地のスーツは、どんな場面でも失礼にあたらず、誠実な印象を与えます。
主役より目立つことを避けるため、黒のフォーマルスーツ(礼服)でも問題ありませんが、祝賀会という華やかな場であることを考えると、ダークスーツの方がやや柔らかい印象になるでしょう。
シャツは、清潔感のある白無地のレギュラーカラーかワイドカラーが基本です。
シワのない、アイロンがけされたシャツを着用するのは最低限のマナーです。
ネクタイは、お祝いの席にふさわしい、明るく上品な色柄を選びましょう。
シルバーグレーやシャンパンゴールド、淡いブルーやピンクのネクタイは、華やかさと品格を両立できます。
ストライプやドット柄も良いですが、あまりに派手な柄やブランドロゴが大きく入ったものは避けるべきです。
靴は、黒の革靴で、ストレートチップかプレーントゥが最もフォーマルです。
事前にきちんと磨き、汚れがないか確認しておきましょう。
靴下は、スーツの色に合わせたダークカラーの無地を選び、座った時に素肌が見えない長さのものを用意します。
意外と見落としがちなのが、ポケットチーフです。
ネクタイの色と合わせたり、シャツに合わせて白のリネン素材のものを選んだりすると、胸元が華やかになり、よりフォーマルな印象が高まります。
女性司会者の服装マナー
女性の場合、服装の選択肢は男性より広いですが、その分、TPOをわきまえた選択が求められます。
最も一般的なのは、上品なワンピースやアンサンブル、スーツスタイルです。
色は、ベージュ、ネイビー、ライトグレー、パステルカラーなど、明るく落ち着いた色合いが好ましいでしょう。
主役である就任者(特に女性の場合)よりも目立ってしまうような、原色や派手な柄、全身白や全身黒のコーディネートは避けるのが賢明です。
素材は、シルクやサテン、レースなど、光沢感や高級感のあるものを選ぶと、お祝いの席にふさわしい華やかさを演出できます。
スカートの丈は、膝が隠れる程度の長さが上品です。
肌の露出は控えめにし、肩が出るデザインの場合は、ジャケットやショール、ボレロなどを羽織るのがマナーです。
アクセサリーは、パールや小ぶりなダイヤモンドのネックレス、イヤリングなど、上品で控えめなものを選び、全体のコーディネートを格上げしましょう。
じゃらじゃらと音を立てるようなアクセサリーは、マイクに音が入ってしまう可能性もあるため避けるべきです。
足元は、肌色のストッキングに、ヒールが高すぎないパンプスを合わせます。
つま先やかかとが出るオープントゥやサンダル、ミュール、そしてカジュアルな印象を与える黒のタイツはフォーマルな場ではNGです。
男女共通の注意点として、何よりも清潔感が大切です。
服装だけでなく、髪型や爪、香り(香水のつけすぎはNG)など、身だしなみ全体に気を配り、誰から見ても好感が持たれるような、品格のある司会者を目指しましょう。
心に響くお祝いの挨拶と祝辞のポイント
就任祝いの会において、司会者の挨拶や、来賓による祝辞は、会の雰囲気を大きく左右する重要な要素です。
司会者は、自身の挨拶だけでなく、祝辞を述べる方を紹介し、会場全体がスピーチに集中できる環境を整える役割も担います。
ここでは、心に響く挨拶と祝辞を演出するためのポイントを解説します。
司会者の開会・閉会の挨拶
司会者の第一声である開会の挨拶は、参加者の注目を集め、これから始まる祝賀会への期待感を高めるための大切なものです。
まず、はっきりとした明るい声で、集まっていただいたことへの感謝を述べます。
そして、本日の会の趣旨、つまり誰のどのような就任をお祝いする会なのかを明確に伝えます。
最後に、会が素晴らしいものになるよう、参加者の協力をお願いする言葉で締めくくると良いでしょう。
一方、閉会の挨拶は、楽しかった会を締めくくり、参加者に満足感と感謝の気持ちを持ってもらうためのものです。
会が無事に終了したことへの感謝、主役の今後の活躍を祈念する言葉、そして参加者の今後の健勝を祈る言葉を述べ、深々としたお辞儀で締めくくります。
開会・閉会ともに、長々と話す必要はありません。
簡潔かつ丁寧に、心を込めて話すことが重要です。
祝辞を述べる方の紹介
来賓に祝辞をお願いする場合、司会者の紹介の仕方が非常に重要になります。
ただ名前と役職を紹介するだけでは不十分です。
紹介する際は、まず、祝辞をいただく来賓の方の正式な会社名、役職、氏名を間違いなく伝えます。
そして、「〇〇様は、新社長〇〇様とは長年にわたり公私ともに親しくされており、本日は〇〇様のご就任を心から喜んでいらっしゃいます」といったように、主役との関係性を一言添えることで、スピーチに深みと温かみが増します。
紹介が終わったら、登壇されるまで拍手を続け、会場全体で歓迎する雰囲気を作りましょう。
祝辞が終わった後も、すぐに次のプログラムに移るのではなく、「〇〇様、心温まるお祝いの言葉、誠にありがとうございました」と、司会者から感謝の言葉を述べ、再度大きな拍手を促すことがマナーです。
祝辞を頼まれた場合のポイント
もし、あなたが司会者ではなく、祝辞を述べる側として依頼された場合にも、いくつかのポイントがあります。
まず、スピーチの時間は3分から5分程度にまとめるのが一般的です。
長すぎるスピーチは、他の参加者を退屈させてしまう可能性があります。
構成としては、以下の流れを意識すると良いでしょう。
- 自己紹介と就任者へのお祝いの言葉
- 就任者との思い出や尊敬する点を具体的に語るエピソード
- 今後の活躍への期待と激励のメッセージ
- 結びの言葉(会社や参加者の発展を祈る言葉など)
特に重要なのが、具体的なエピソードです。
「仕事熱心で素晴らしい方です」という抽象的な言葉よりも、「〇〇のプロジェクトで困難に直面した際、彼(彼女)は最後まで諦めずにチームをまとめ上げ、見事に成功へと導きました」といった具体的なエピソードを語る方が、人柄が伝わり、聞き手の心を打ちます。
また、内輪すぎる話や自慢話、暴露話は避け、誰が聞いても不快にならない内容を心がけましょう。
そして、原稿を読み上げるだけでなく、できるだけ顔を上げ、会場の参加者や主役の顔を見ながら、語りかけるように話すことが、気持ちを伝える上で非常に大切です。
就任祝いのプレゼントには胡蝶蘭が最適

就任祝いの会を企画する際、またはゲストとして招かれた際に、心のこもったプレゼントを贈りたいと考える方は多いでしょう。
数ある贈り物の中でも、特に社長や役員の就任祝いといったフォーマルなお祝いのシーンで圧倒的な支持を得ているのが「胡蝶蘭」です。
なぜ、これほどまでに胡蝶蘭が選ばれるのでしょうか。
その理由を知ることで、贈り物の価値がさらに高まります。
縁起の良い花言葉
胡蝶蘭が持つ花言葉は「幸福が飛んでくる」です。
蝶が舞うような花の姿から、このような縁起の良い花言葉が付けられました。
これは、新たな役職に就き、これから更なる発展を目指す方への贈り物として、これ以上ないほどふさわしいメッセージと言えるでしょう。
また、鉢植えの胡蝶蘭は「根付く」という意味合いも持ち合わせているため、「新しい役職に根付き、地域や会社に貢献し、長く活躍してほしい」という願いも込めることができます。
品格と高級感のある佇まい
胡蝶蘭の最大の魅力は、その優雅で気品あふれる花の姿です。
整然と並んだ大輪の花々は、見る人に感動と豪華な印象を与えます。
企業の受付や社長室に飾られていることも多く、その場を一瞬で華やかにし、格調高い空間を演出する力があります。
大切な取引先や、尊敬する上司の就任祝いなど、絶対に失敗したくないフォーマルな贈り物において、胡蝶蘭が持つ「きちんと感」と「高級感」は、他のどんな花にも代えがたい価値を持っています。
長く楽しめる生命力
一般的な切り花の花束は、どんなに美しくても1週間から10日ほどで枯れてしまいます。
しかし、胡蝶蘭の鉢植えは非常に生命力が強く、お手入れ次第では1ヶ月から3ヶ月以上もの長期間、美しい花を咲かせ続けます。
贈られた側は、長い間その美しい花々を眺めながら、お祝いしてくれた人々の温かい気持ちを思い出すことができるでしょう。
忙しい就任直後の時期に、頻繁に水やりをする必要がないという手入れの手軽さも、喜ばれるポイントの一つです。
ビジネスシーンでの定番という安心感
胡蝶蘭は、開店祝い、開業祝い、そして就任祝いなど、あらゆるビジネスシーンでのお祝いギフトとして、長年にわたり選ばれ続けてきた実績があります。
いわば「お祝いの王道」であり、これを選んでおけば間違いがないという絶対的な安心感があります。
何を贈るべきか迷った際には、この定番を選ぶことが、相手への敬意を示す最良の方法となることも少なくありません。
最近では、インターネット通販で手軽に高品質な胡蝶蘭を注文できるようになりました。
立て札やラッピングのサービスも充実しており、贈り先の住所へ直接配送してくれるため、忙しい方でもスマートに心のこもったお祝いを届けることが可能です。
就任祝いのプレゼント選びに迷ったら、縁起が良く、品格があり、長く楽しめる胡蝶蘭を贈ることを強くおすすめします。
その美しい花は、きっと相手の輝かしい未来を祝福してくれることでしょう。
就任祝いの司会でそのまま使える台本と例文集
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 開会から閉会まで流れに沿った司会進行の例文
- 主役を紹介する際のスマートな言い回し
- 乾杯の挨拶を依頼する時の丁寧なフレーズ
- 会を和ませる歓談中のアナウンス例
- 避けるべき忌み言葉と言い換え表現
- 最高の就任祝いの司会で輝かしい門出を演出しよう
開会から閉会まで流れに沿った司会進行の例文

ここでは、就任祝いの司会進行で実際に使える、開会から閉会までの一連の台本例文を紹介します。
この例文をベースに、会の雰囲気や主役の人柄に合わせて、言葉遣いや表現をアレンジしてみてください。
()内は、状況に応じた補足や司会者の動きを示しています。
1. 開会の辞
「皆様、本日はお忙しい中、株式会社〇〇 新社長 〇〇 〇〇 様の社長ご就任を祝う会に、多数ご臨席賜りまして、誠にありがとうございます。
わたくし、本日の司会進行を務めさせていただきます、〇〇部の〇〇と申します。
至らぬ点も多々あるかと存じますが、精一杯務めさせていただきますので、皆様どうぞ最後までごゆっくりとお過ごしください。
それでは、これより、『株式会社〇〇 〇〇 〇〇 様 社長就任祝賀会』を開会いたします。」
(一礼し、大きな拍手を促す)
2. 主催者挨拶
「開会にあたりまして、本祝賀会の発起人を代表いたしまして、〇〇会長よりご挨拶を申し上げます。
〇〇会長、よろしくお願いいたします。」
(挨拶後)
「〇〇会長、ありがとうございました。」
3. 来賓祝辞
「続きまして、ご来賓の皆様よりお祝いの言葉を頂戴したく存じます。
はじめに、〇〇株式会社 代表取締役社長 〇〇 〇〇 様よりご祝辞を賜ります。
〇〇様は、〇〇新社長とは旧知の仲でいらっしゃり、本日のご就任を心待ちにされていたと伺っております。
それでは、〇〇様、よろしくお願いいたします。」
(祝辞後)
「〇〇様、心温まるご祝辞、誠にありがとうございました。」
(もう一名いる場合)
「続きまして、〇〇組合 理事長 〇〇 〇〇 様よりご祝辞を頂戴いたします。
よろしくお願いいたします。」
4. 就任者(主役)挨拶
「皆様、大変お待たせいたしました。
ここで、本日の主役でございます、株式会社〇〇 新社長 〇〇 〇〇 様より、ご就任のご挨拶と今後の抱負についてお言葉を頂戴いたします。
皆様、盛大な拍手でお迎えください。
〇〇新社長、よろしくお願いいたします。」
(挨拶後)
「〇〇新社長、力強い決意のこもったご挨拶、誠にありがとうございました。
皆様、〇〇新社長の今後のご活躍を祈念いたしまして、今一度盛大な拍手をお願いいたします。」
5. 乾杯
「それでは、これより祝宴に移らせていただきます。
つきましては、乾杯の音頭を、〇〇株式会社 専務取締役 〇〇 〇〇 様にお願いしたく存じます。
皆様、お手元のグラスのご用意をお願いいたします。
それでは〇〇専務、よろしくお願いいたします。」
(乾杯後)
「〇〇専務、ありがとうございました。
それでは、皆様、どうぞごゆっくりとご歓談、お食事をお楽しみください。」
6. 祝電披露
(歓談が盛り上がっている最中に)
「皆様、ご歓談のところ、誠に恐れ入ります。
ここで、〇〇新社長のご就任に際し、お寄せいただきましたお祝いのメッセージの一部を、ご紹介させていただきます。」
(祝電を数通読み上げる)
「この他にも多数のお祝いを頂戴しております。
誠にありがとうございました。」
7. 閉会の辞(中締め)
「皆様、楽しい時間はあっという間に過ぎるもので、誠に名残惜しいのではございますが、そろそろお開きの時間が近づいてまいりました。
宴の結びに、〇〇株式会社 〇〇本部長より、締めの挨拶と三本締めを執り行いたいと存じます。
〇〇本部長、よろしくお願いいたします。」
(挨拶と三本締めの後)
「〇〇本部長、ありがとうございました。
皆様、ご協力ありがとうございます。」
8. 閉会宣言
「皆様、本日はお忙しい中、最後までお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。
〇〇新社長の今後の益々のご健勝と、株式会社〇〇の更なるご発展、ならびにご臨席の皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。
これをもちまして、『株式会社〇〇 〇〇 〇〇 様 社長就任祝賀会』をお開きとさせていただきます。
お帰りの際は、お忘れ物などなさいませんよう、お気をつけてお帰りください。
本日は誠にありがとうございました。」
(深々と一礼する)
主役を紹介する際のスマートな言い回し
就任祝いの司会において、主役である新就任者を紹介する場面は、最も重要な見せ場の一つです。
単に名前と役職を告げるだけでなく、その人柄や功績に触れ、参加者からの期待感を高めるようなスマートな紹介が求められます。
ここでは、様々な状況で使える、主役を紹介する際の言い回しやフレーズの例文をいくつかご紹介します。
基本的な紹介のフレーズ
まずは、最もシンプルで丁寧な基本形です。
どんな場面でも使うことができます。
「それでは、本日の主役でございます、この度、株式会社〇〇の代表取締役社長にご就任されました、〇〇 〇〇様をご紹介いたします。皆様、盛大な拍手でお迎えください。」
功績や実績を交えた紹介
主役のこれまでの実績に触れることで、就任への説得力と期待感を高めることができます。
事前にリサーチした情報を基に、具体的な功績を簡潔に述べましょう。
「続きまして、本日の主役にご登場いただきます。長年にわたり、当社の主力事業である〇〇プロジェクトを牽引し、今日の成長の礎を築かれた手腕は、皆様もご存知のことと存じます。その確かな実績とリーダーシップを基に、この度、専務取締役にご就任されました、〇〇 〇〇様です。どうぞ、大きな拍手をお願いいたします。」
人柄や人間的魅力に焦点を当てた紹介
特に社内のメンバーが多く集まるような、少し和やかな雰囲気の会では、人柄が伝わるような紹介も喜ばれます。
親しみやすさや温かみを演出できるでしょう。
「お待たせいたしました。いよいよ本日の主役の登場です。常に部下一人ひとりに気を配り、その温かいお人柄で多くの社員から慕われております。時には厳しく、しかしそれ以上に深い愛情を持って我々を導いてくださる、私達の新しいリーダー、〇〇 〇〇新本部長です。皆様、どうぞ温かい拍手でお迎えください。」
ユーモアを少し交えた紹介
会の雰囲気や主役との関係性によっては、少しユーモアを交えることで、場が和み、親近感が湧きます。
ただし、敬意を欠いた表現にならないよう、さじ加減には注意が必要です。
「さて、皆様、お待ちかねの真打ちにご登場願いましょう。大変な食通としても知られ、彼のおすすめのお店にハズレはないと評判ですが、これからは会社の舵取りにおいても、その鋭い目利きを発揮してくださるに違いありません。株式会社〇〇の新取締役、〇〇 〇〇様です。よろしくお願いいたします。」
紹介する際のポイント
- 名前や役職は絶対に間違えない。不安な場合は、事前に本人に確認を取る。
- 長々と話しすぎない。紹介コメントは簡潔に、要点をまとめて話す。
- 紹介する際は、主役がいる方向へ体を向け、敬意を示す。
- 紹介の言葉と共に、会場全体に拍手を促し、歓迎ムードを最大限に高める。
これらの例文やポイントを参考に、あなたらしい言葉で、主役の魅力を最大限に引き出す紹介を心がけてみてください。
心のこもった紹介は、主役にとって何より嬉しいお祝いの言葉となるはずです。
乾杯の挨拶を依頼する時の丁寧なフレーズ

祝賀会における乾杯は、お祝いの気持ちを一つにし、楽しい祝宴のスタートを告げる重要なセレモニーです。
司会者は、乾杯の音頭を取る方へスムーズにバトンを渡し、会場全体が一体となれるような雰囲気を作り出す役割を担います。
ここでは、乾杯の挨拶を依頼する際の丁寧なフレーズと、その前後の流れについて解説します。
依頼する相手の選定
まず、誰に乾杯の音頭を依頼するかは、事前に主催者と打ち合わせておく必要があります。
一般的には、主役にとって重要で、かつ役職の高い方が選ばれます。
例えば、主催者の次に高い役職の方や、主役が特にお世話になっている取引先の重役などが適任です。
依頼する方が決まったら、その方の正式な会社名、役職、氏名を正確に把握し、読み間違えのないように準備しておきましょう。
依頼の基本的なフレーズ
就任者の挨拶が終わり、いよいよ祝宴に移るというタイミングで、乾杯の案内をします。
以下が基本的なフレーズです。
「〇〇新社長、力強いご挨拶、誠にありがとうございました。
それでは、これより皆様お待ちかねの祝宴に移らせていただきたく存じます。
つきましては、乾杯の音頭を、〇〇株式会社 専務取締役 〇〇 〇〇様にお願い申し上げます。
〇〇様は、〇〇新社長が若手の頃からその成長を見守ってこられた、最も信頼する先輩でいらっしゃいます。
皆様、お手元にグラスのご用意はよろしいでしょうか。
それでは、〇〇専務、よろしくお願いいたします。」
フレーズ作成のポイント
1. **クッション言葉を使う**
「それでは」「つきましては」といったクッション言葉を入れることで、話の流れがスムーズになります。
2. **依頼相手を紹介する**
ただ名前を告げるだけでなく、「〇〇様にお願い申し上げます」と、丁寧な依頼の形にすることが大切です。
また、例文のように、主役との関係性を一言付け加えることで、なぜその方が音頭を取るのかが参加者に伝わり、より心のこもった乾杯になります。
3. **参加者へのアナウンス**
「皆様、お手元のグラスのご用意をお願いいたします」という一言は非常に重要です。
このアナウンスにより、参加者は乾杯の準備をすることができ、スムーズにセレモニーに入ることができます。
4. **依頼相手へのバトンパス**
最後に「〇〇様、よろしくお願いいたします」と、はっきりと依頼相手にバトンを渡す言葉で締めくくります。
司会者がここまで話したら、あとは依頼された方にマイクを渡し、少し下がって待機します。
乾杯後の流れ
依頼された方が「乾杯!」と発声し、会場全体が唱和した後、司会者は再び前に出ます。
そして、感謝の言葉を述べることを忘れないでください。
「〇〇専務、ありがとうございました。
高らかなご発声で、祝宴の幕開けに華を添えていただきました。
それでは、皆様、これよりお時間の許す限り、どうぞごゆっくりとご歓談、並びにお食事をお楽しみくださいませ。」
この一連の流れをスムーズに行うことで、祝賀会は一体感を持ち、和やかな祝宴へと移行していくことができます。
丁寧な言葉遣いと、参加者への細やかな配慮が、司会者の腕の見せ所です。
会を和ませる歓談中のアナウンス例
乾杯が終わり、祝宴が始まると、会場は和やかな歓談の時間に移ります。
しかし、司会者の仕事はここで終わりではありません。
歓談中も、参加者がより楽しめるように、また、会がスムーズに進行するように、適切なタイミングでアナウンスを入れる必要があります。
ここでは、会を和ませ、円滑に進めるための歓談中のアナウンス例をいくつかご紹介します。
主役との歓談を促すアナウンス
歓談が始まると、主役の周りには挨拶の列ができがちです。
一方で、少し遠くの席にいる人は、話しかけるタイミングを逃してしまうこともあります。
そんな時に、司会者から一言促すことで、より多くの人が主役とお祝いの言葉を交わすきっかけを作れます。
「皆様、ご歓談、楽しんでいらっしゃいますでしょうか。
本日の主役、〇〇新社長も、皆様とお話できることを心より楽しみにしております。
まだご挨拶がお済みでない方も、ぜひこの機会に〇〇新社長の席まで足をお運びいただき、直接お祝いの言葉をお伝えいただければと存じます。」
食事や飲み物を勧めるアナウンス
会場の料理や飲み物について触れることで、参加者がよりリラックスして食事を楽しめる雰囲気を作ります。
「皆様、テーブルのお食事は、〇〇ホテル自慢のメニューでございます。
どうぞご遠慮なく、たくさんお召し上がりください。
また、お飲み物のおかわりは、お近くのスタッフまでお気軽にお声がけくださいませ。」
写真撮影を促すアナウンス
祝賀会は記念すべき日です。
写真撮影の時間を設けることで、思い出を形に残すことができます。
「皆様、ご歓談のところ恐れ入ります。
せっかくの機会でございますので、ここで〇〇新社長との記念撮影の時間を設けたいと存じます。
部署ごと、グループごとにお撮りしますので、カメラをお持ちの方は、どうぞステージ前までお集まりください。」
祝電披露前のアナウンス
歓談の途中で祝電を披露する際は、一度参加者の注目を集める必要があります。
唐突に始めるのではなく、クッションとなるアナウンスを入れましょう。
「皆様、ご歓談のところ、まことに恐縮ですが、少々お耳を拝借いたします。
〇〇新社長のご就任にあたり、会場にお越しになれなかった皆様からも、たくさんのお祝いのメッセージが届いております。
ここで、その一部をわたくしから代読させていただきます。」
終了時間が近いことを知らせるアナウンス
閉会が近づいてきたら、事前にアナウンスを入れることで、参加者は心の準備ができます。
突然「閉会です」と告げるよりも、丁寧な印象を与えます。
「皆様にお知らせいたします。
楽しい時間はあっという間に過ぎるもので、まことに名残惜しいのですが、閉会のお時間まで、あと30分ほどとなりました。
まだお話足りない方もいらっしゃると存じますが、どうぞ最後までごゆっくりとお過ごしください。
また、お飲み物のラストオーダーとなりますので、ご注文がおありの方はお近くのスタッフまでお願いいたします。」
これらのアナウンスは、あくまでも歓談の邪魔にならないように、タイミングと声のトーンに配慮することが大切です。
会場の雰囲気を見ながら、適切な一言を添えることで、司会者としての評価は格段に上がるでしょう。
避けるべき忌み言葉と言い換え表現

お祝いの席である就任祝いの会では、縁起の悪い言葉や、その場にふさわしくない「忌み言葉(いみことば)」の使用を避けるのがマナーです。
司会者はもちろん、挨拶や祝辞を述べる方も、これらの言葉を無意識に使ってしまわないように注意が必要です。
知らずに使ってしまうと、せっかくのお祝いムードに水を差したり、相手に不快な思いをさせてしまったりする可能性があります。
ここでは、就任祝いの場で特に避けるべき忌み言葉と、そのスマートな言い換え表現を一覧でご紹介します。
事前に確認し、台本作成やスピーチの準備に役立ててください。
倒産や業績悪化を連想させる言葉
会社の未来を祝う席で、衰退をイメージさせる言葉は最大のタブーです。
| 忌み言葉 | 言い換え表現 |
|---|---|
| 倒れる、潰れる | 業績が厳しくなる、経営が傾く |
| 終わる、終了する | お開きにする、めでたく迎える |
| 辞める、退く | ご勇退、ご卒業、新たな道に進む |
| 赤、赤字 | 損失、マイナス |
| 傾く、落ちる | 変化する、推移する |
| 閉じる、締める | 結びとする、お開きにする |
苦労や困難を連想させる言葉
新任者の前途が多難であることを暗示するような言葉も避けましょう。
過去の苦労話をする際にも、表現には注意が必要です。
| 忌み言葉 | 言い換え表現 |
|---|---|
| 苦しい、大変、厳しい | 試練の時、大きな挑戦、やりがいのある |
| 消える、無くなる | 姿を変える、見えなくなる |
| 衰える、弱る | 落ち着く、円熟する |
| 病む、壊れる | ご療養、お休みされる |
重ね言葉
再婚や不幸が続くことを連想させるため、結婚式などで特に嫌われる「重ね言葉」ですが、就任祝いの場でも、同じ役職を何度も繰り返す(=長く続かない)という意味合いを避けるため、使わない方が無難とされています。
| 忌み言葉 | 言い換え表現 |
|---|---|
| 重ね重ね、くれぐれも | 加えて、深く、十分に |
| ますます、いよいよ | さらに、一段と |
| たびたび、しばしば | よく、頻繁に |
これらの言葉は、日常会話では何気なく使ってしまうものも多いため、特に意識して準備することが重要です。
台本を作成したら、忌み言葉が含まれていないか、必ず声に出して読み返し、チェックする習慣をつけましょう。
もし、スピーチの途中でうっかり使ってしまった場合でも、慌てて訂正するとかえって目立ってしまいます。
その場合は、気にせず堂々と話を続ける方がスマートです。
言葉一つひとつに心を配ることが、品格のある司会進行に繋がります。
最高の就任祝いの司会で輝かしい門出を演出しよう
これまで、就任祝いの司会を成功させるための準備、心構え、そして具体的な台本やマナーについて詳しく解説してきました。
司会という大役は、確かに責任が重く、プレッシャーを感じるかもしれません。
しかし、それは同時に、大切な方の人生の節目に立ち会い、その輝かしい門出を演出するという、非常にやりがいのある素晴らしい役割でもあります。
あなたの心のこもった言葉と、細やかな配慮に満ちた進行が、祝賀会の雰囲気を作り上げ、主役である新就任者の喜びを何倍にも大きくするのです。
成功の鍵は、何よりも周到な「準備」にあります。
この記事で紹介したポイントを踏まえ、あなた自身の言葉で台本を練り上げ、何度も声に出して練習を重ねてください。
主役の人柄や功績を深く理解し、参加者全員が楽しめるような会の流れをイメージすることができれば、自然と自信が湧いてくるはずです。
当日は、練習してきた台本を信じつつも、あまりがんじがらめにならず、会場の雰囲気を感じながら、笑顔で臨むことを忘れないでください。
あなたの明るい表情と、祝福の気持ちがこもった声が、会場全体を温かいお祝いムードで包み込みます。
また、心のこもったお祝いは、司会進行だけではありません。
「幸福が飛んでくる」という素晴らしい花言葉を持つ胡蝶蘭のような贈り物は、言葉以上に雄弁にあなたの祝福の気持ちを伝えてくれるでしょう。
会の会場に飾られた美しい胡蝶蘭は、その場を華やかに彩るだけでなく、閉会後も新就任者のオフィスで長く咲き続け、この日の感動を伝え続けてくれます。
最高の就任祝いの司会を務め上げること、それは、新就任者にとって忘れられない最高のプレゼントとなります。
この記事が、その大役を見事に果たし、素晴らしい祝賀会を創り上げるための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
あなたの司会で、主役の輝かしい未来への第一歩を、盛大に祝福してあげてください。
fa-file-powerpoint-o
この記事のまとめ
- 就任祝いの司会は会の演出家であり指揮者である
- 成功の鍵は主役への敬意と周到な事前準備にある
- 台本は具体的なセリフや動きまで書き込むと安心
- 司会者の服装は主役を引き立てる品格のある装いが基本
- 男性はダークスーツ女性は上品なワンピースなどが望ましい
- 挨拶や祝辞は簡潔にまとめ具体的なエピソードを交えると心に響く
- 乾杯の依頼は丁寧な言葉遣いと参加者への配慮が重要
- 歓談中も適切なアナウンスで会を円滑に進行させる
- お祝いの席では縁起の悪い忌み言葉の使用を避けるマナーが大切
- 「終わる」は「お開きにする」などスマートな言い換えを心がける
- 就任祝いのプレゼントには縁起の良い胡蝶蘭が最適
- 胡蝶蘭の花言葉「幸福が飛んでくる」は門出の祝福にぴったり
- 通販サイトを利用すれば高品質な胡蝶蘭を手軽に贈ることができる
- 当日は練習を信じ笑顔で臨むことが最高の司会につながる
- 心のこもった司会進行が新就任者への最高の贈り物となる