ビジネスシーンにおいて、取引先や上司、同僚から訃報の連絡を受ける場面は突然訪れるものです。
このような状況で、お悔やみ 電話 ビジネスにおける適切な対応ができるかどうかは、社会人としての信頼を左右する重要な要素となります。
いざという時に慌てないためには、しっかりとしたマナーや相手別の文例を事前に理解しておくことが欠かせません。
電話をかけるタイミングや、伝えるべきことの要点を押さえるのはもちろんのこと、うっかり使ってしまいがちな忌み言葉についても注意点として知っておく必要があります。
また、電話が繋がらない場合の対処法として、メールでの連絡や弔電を手配する方法も心得ておくと、より丁寧な対応が可能になるでしょう。
この記事では、そうしたお悔やみ 電話 ビジネスに関するあらゆる作法を網羅的に解説し、あなたの不安を解消します。
fa-hand-pointer-o
この記事で分かる事、ポイント
- お悔やみ電話をかける際の基本的なビジネスマナー
- 上司や取引先など相手別の具体的な会話文例
- 電話をかけるべき、あるいは避けるべきタイミング
- 使ってはいけない忌み言葉とその言い換え表現
- 電話以外の伝達手段であるメールや弔電の送り方
- 香典や供花を手配する際の注意点と選び方
- 突然の訃報にも冷静かつ失礼なく対応するための知識
お悔やみ 電話 ビジネスで押さえるべき基本マナー
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- まずは相手別の適切な対応を知る
- 電話をかけるタイミングの判断基準
- そのまま使える場面ごとの文例集
- 最低限伝えるべきこととは何か
- 知らないと失礼にあたる忌み言葉
お悔やみ 電話 ビジネスの場面では、日常的なコミュニケーションとは異なる特別な配慮が求められます。
故人を悼む気持ちを伝えつつも、ご遺族や関係者の負担にならないよう、マナーを守った行動を心がけることが重要です。
この章では、ビジネスシーンにおけるお悔やみの電話で、最低限押さえておくべき基本的なマナーについて詳しく解説していきます。
相手との関係性に応じた対応の違いから、電話をかける時間帯、そして具体的な言葉選びまで、一つひとつ確認していきましょう。
まずは相手別の適切な対応を知る

お悔やみの電話をかける際、まず意識すべきなのは、電話をかける相手が誰であるかという点です。
相手の立場や関係性によって、言葉遣いや伝えるべき内容が微妙に異なります。
ここでは、主なケースとして「上司・同僚」「取引先」の2つのパターンに分け、それぞれの適切な対応方法を解説します。
上司や同僚、そのご家族へ連絡する場合
会社の内部関係者である上司や同僚、またはそのご家族に連絡する際は、丁寧でありながらも、事務的な確認事項を簡潔に伝える必要があります。
会社としての対応(弔電、供花、香典、代表者の弔問など)をどうするか、速やかに確認・決定する必要があるからです。
まず、お悔やみの言葉を述べた後、故人との関係、亡くなられた日時や原因(差し支えなければ)、通夜・告別式の日時と場所などを確認します。
ただし、ご遺族は精神的にも時間的にも余裕がない状態ですので、長電話は絶対に避けなければなりません。
あくまで手短に、必要な情報を伺う姿勢を徹底してください。
特に、死因などプライベートな内容については、相手から話されない限りはこちらから尋ねるべきではありません。
会社として誰が窓口になるのかを明確にし、今後の連絡はその担当者から行う旨を伝えると、ご遺族の負担を軽減できるでしょう。
取引先の方へ連絡する場合
取引先の方へお悔やみの電話をする場合は、さらに慎重な対応が求められます。
会社の代表として連絡しているという意識を強く持ち、失礼のないように細心の注意を払いましょう。
まずは、会社名と氏名を名乗り、お悔やみの言葉を述べます。
こちらも長電話は厳禁です。
ご遺族の状況を気遣い、「大変な時に申し訳ございません」といったクッション言葉を添えるのがマナーです。
弔問や香典については、先方が香典などを辞退されているケースもあるため、まずは「お伺いしてもよろしいでしょうか」と確認するのが良いでしょう。
もし弔問に伺う場合は、後任担当者の紹介や業務の引き継ぎに関する話は、その場では避けるのが賢明です。
そういったビジネス上の話は、後日改めて、別の担当者から連絡するのが適切な流れとなります。
お悔やみの場では、故人を偲ぶ気持ちを伝えることに専念しましょう。
電話をかけるタイミングの判断基準
お悔やみの電話をかけるタイミングは、非常に重要であり、判断に迷うことも多いでしょう。
早すぎても、遅すぎても失礼にあたる可能性があります。
ここでは、電話をかけるべき適切な時間帯と、逆に避けるべき状況について解説します。
訃報を受けたら、なるべく早くが基本
原則として、訃報を受けたらなるべく早いタイミングで連絡するのがマナーとされています。
時間が経てば経つほど、相手も「知っているはずなのに連絡がない」と感じてしまうかもしれません。
ただし、「早いタイミング」といっても、深夜や早朝などの非常識な時間帯は避けるべきです。
ご遺族は、訃報直後から様々な手続きや準備に追われています。
そのため、電話をかける時間帯には最大限の配慮が必要です。
一般的には、午前9時から午後6時くらいまでの、日中の時間帯が望ましいとされています。
もし夜間に訃報を知った場合は、翌日の午前中に改めて連絡するのが良いでしょう。
すぐに電話をかける前に、まずは一呼吸おいて、ご遺族の状況を想像することが大切です。
避けるべき時間帯や状況
お悔やみの電話を避けるべき時間帯や状況も存在します。
まず、前述の通り、深夜や早朝の連絡は絶対に避けなければなりません。
また、食事時である昼の12時前後や、夕食の時間帯である午後6時以降も、相手の迷惑になる可能性が高いため、避けた方が無難でしょう。
さらに、通夜や告別式の最中、またはその直前直後は、ご遺族が最も慌ただしくしている時間帯です。
このタイミングでの電話は、取り込み中の相手を妨げることになり、失礼にあたります。
もし、どうしても連絡が取れなかったり、タイミングが合わなかったりした場合は、無理に電話をせず、後述するメールや弔電といった別の手段を検討することも重要です。
相手の状況を最優先に考え、柔軟に対応する姿勢が求められます。
そのまま使える場面ごとの文例集

実際にお悔やみの電話をかける際、どのような言葉で伝えれば良いのか、戸惑う方は少なくありません。
ここでは、様々なシチュエーションでそのまま使える具体的な文例を紹介します。
相手や状況に合わせて、表現を調整して活用してください。
- 上司の身内に不幸があった場合
- 同僚本人から連絡を受けた場合
- 取引先の担当者から訃報を受けた場合
文例1:上司の奥様が亡くなられた場合
「〇〇部〇〇課の〇〇です。ただいま、〇〇課長からご連絡いただき、奥様の訃報に接しました。この度は誠に残念なことで、心からお悔やみ申し上げます。ご家族の皆様もさぞお力落としのことと存じます。何か私にできることがございましたら、何なりとお申し付けください。大変な時に恐縮ですが、通夜・告別式の日程がお決まりでしたら、お教えいただけますでしょうか。」
この文例のポイントは、まずお悔やみの言葉を述べ、相手を気遣う一言を添えている点です。
その上で、会社としての対応に必要な情報を簡潔に伺うという構成になっています。
文例2:同僚の父親が亡くなられたと本人から聞いた場合
「〇〇(同僚の名前)です。たった今、お父様が亡くなられたと伺いました。突然のことで、言葉も見つかりません。心よりご冥福をお祈りいたします。大変な時に申し訳ないけれど、仕事のことは心配しないで、ご家族との時間を大切にしてください。業務の引き継ぎなどは、こちらでうまく対応しておくので、安心して任せてください。」
親しい同僚が相手であっても、お悔やみの場では丁寧な言葉遣いを基本とします。
仕事の心配をさせないよう、具体的な配慮の言葉を添えることで、相手を安心させることができます。
文例3:取引先の社長が亡くなられたと担当者から連絡があった場合
「株式会社〇〇の〇〇と申します。いつもお世話になっております。ただいま、御社の〇〇様より、〇〇社長様の訃報に接し、大変驚いております。生前はひとかたならぬご厚情を賜り、誠にありがとうございました。謹んでお悔やみ申し上げます。よろしければ、通夜にご弔問に伺いたいのですが、ご都合はいかがでしょうか。また、誠に恐縮ですが、香典や供花はご辞退などされていませんでしょうか。」
取引先へは、まず自社の社名と氏名を明確に伝えます。
故人への感謝の気持ちを述べ、弔問や香典について、相手の意向を確認する姿勢を示すことが大切です。
最低限伝えるべきこととは何か
お悔やみの電話は、手短に済ませることが大前提です。
ご遺族の負担を考え、長々と話すのはマナー違反となります。
そのため、電話をかける前に、何を伝え、何を確認すべきかを整理しておくことが重要です。
ここでは、最低限伝えるべき項目をリストアップして解説します。
- 自己紹介(会社名・部署名・氏名)
- お悔やみの言葉
- 相手を気遣う言葉
- 弔問や参列の可否確認
- 通夜・告別式の日時と場所の確認
- 喪主の氏名と故人との続柄の確認
まず最初に、自分が誰であるかを明確に伝えます。
次に、「この度はご愁傷様です」「心よりお悔やみ申し上げます」といったお悔やみの言葉を述べます。
そして、「お力落としのことと存じますが、どうぞご自愛ください」のように、相手の心身を気遣う言葉を添えましょう。
その上で、会社として弔問に伺ってよいか、また香典や供花を受け付けているかを確認します。
もし参列が可能であれば、通夜・告別式の日時と場所を伺います。
これらの情報は、会社への報告や弔電の手配に必要です。
最後に、弔電や香典の宛名となる喪主の氏名と、故人との続柄を確認しておくと、後の手続きがスムーズに進みます。
これらの項目を、簡潔かつ丁寧に、順序立てて伝えることを意識してください。
知らないと失礼にあたる忌み言葉
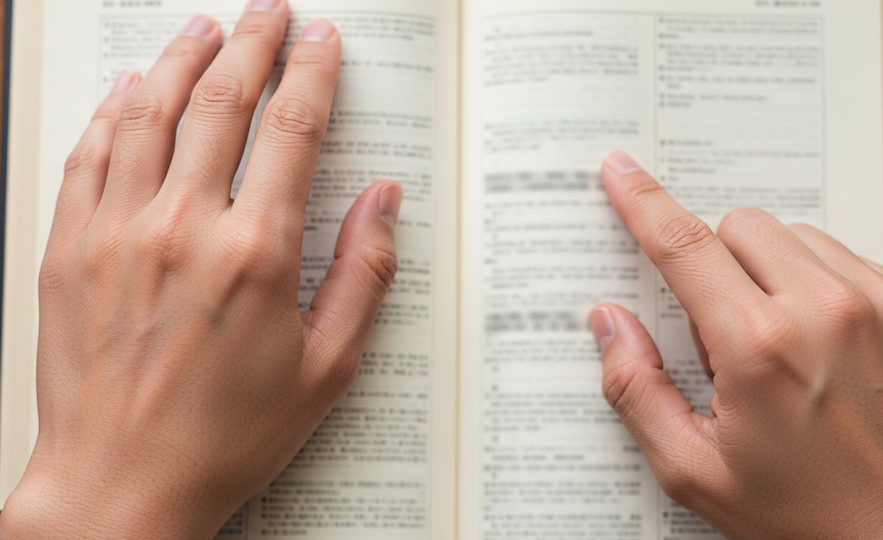
お悔やみの場では、日常的に使っている言葉が、意図せず相手を傷つけたり、不快にさせたりすることがあります。
これらを「忌み言葉」と呼び、使用を避けるのがマナーです。
特に、不幸が重なることや、死を直接的に連想させる言葉はタブーとされています。
ここでは、代表的な忌み言葉とその言い換え表現をまとめました。
重ね言葉
重ね言葉は、不幸が重なる、繰り返すことを連想させるため、お悔やみの場では避けるべきとされています。
| 忌み言葉(重ね言葉) | 言い換え表現 |
|---|---|
| 重ね重ね | 加えて、深く |
| くれぐれも | どうぞ、十分に |
| またまた | 改めて |
| しばしば | よく |
| 追って | 後ほど |
例えば、「重ね重ね残念です」ではなく、「加えて、大変残念に思います」のように言い換えることができます。
不幸が続くことを連想させる言葉
「続く」「再び」といった言葉も、不幸の連続を想起させるため、使用を避けます。
- 続く → 引き続き、これからも
- 再び → 改めて
- 追伸 → 付け加えて申し上げます
直接的な表現
「死ぬ」「生きる」といった直接的な表現は避け、より丁寧で婉曲的な言葉遣いを心がけます。
ご遺族の心情に配慮し、ショックを与えないためのマナーです。
| 直接的な表現 | 言い換え表現 |
|---|---|
| 死亡、死んだ | ご逝去、亡くなられた |
| 生きている時 | ご生前、お元気でいらした頃 |
これらの忌み言葉は、無意識に使ってしまうことが多いものです。
お悔やみの電話をかける前には、一度これらの言葉を確認し、使わないように意識することが大切です。
お悔やみ 電話 ビジネスでの応用と注意点
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- 電話が繋がらない場合の対処法
- メールで連絡する際の注意点
- 弔電を手配する際のマナー
- 香典や供花の相談を受けた場合
- お悔やみ 電話 ビジネスの総まとめ
お悔やみ 電話 ビジネスの基本的なマナーを理解した上で、次に実際の場面で起こりうる様々な状況への応用と、さらなる注意点について解説します。
例えば、相手が電話に出られなかった場合や、そもそも電話での連絡がはばかられる状況など、イレギュラーな事態にもスマートに対応できる知識を身につけておきましょう。
また、お悔やみの気持ちを形にする弔電や供花についても、正しい知識を持つことで、より心のこもった対応が可能となります。
電話が繋がらない場合の対処法

お悔やみの電話をかけても、相手がすぐに出られるとは限りません。
ご遺族は非常に取り込んでいるため、電話に出られない、あるいは留守番電話になっているケースも多いでしょう。
そのような場合に、どのように対処すべきかを知っておくことも大切です。
留守番電話にメッセージを残すべきか
もし相手が電話に出ず、留守番電話に切り替わった場合、メッセージを残すべきか迷うかもしれません。
結論から言うと、お悔やみのメッセージを留守番電話に吹き込むのは、避けた方が無難です。
声のトーンや言葉選びが難しく、一方的に話すことでかえって事務的な印象を与えてしまう可能性があるからです。
また、ご遺族が後でメッセージを確認する手間を増やすことにもなりかねません。
何度も電話をかけ直すのも、相手の負担を増やすことになるため、避けるべきです。
一度かけて繋がらなかった場合は、時間を置いてかけ直すか、後述するメールなどの別の手段を検討するのが良いでしょう。
時間を置いてかけ直す際の注意点
一度で繋がらなかった場合に、少し時間を置いてから再度電話をかけること自体は問題ありません。
ただし、その際にもいくつか注意点があります。
まず、執拗に何度もかけ続けるのは絶対にやめましょう。
多くても、2〜3回が限度と考えるべきです。
また、かけ直す際も、前述したように早朝や深夜、食事時などの時間帯は避けるように配慮が必要です。
もし、何度か試みても繋がらないようであれば、その日は諦めて、翌日に改めて連絡するか、他の方法を考えるのが賢明な判断と言えます。
電話が繋がらないのは、相手がそれだけ忙しい、あるいは電話に出られる心境ではないというサインかもしれません。
その状況を察し、相手を気遣うことが最も重要です。
メールで連絡する際の注意点
近年では、お悔やみの連絡を電話ではなくメールで行うケースも増えてきました。
特に、相手が多忙で電話に出られないことが想定される場合や、訃報を多くの関係者に一斉に知らせる必要がある場合などには、メールが有効な手段となり得ます。
しかし、メールは電話と違って声のトーンが伝わらない分、言葉選びにはより一層の配慮が必要です。
メールを送るのが許容される相手と状況
本来、お悔やみは直接会って伝えるか、電話で伝えるのが正式なマナーとされています。
そのため、メールでの連絡は略式であるという認識を持っておく必要があります。
メールが許容されるのは、主に親しい間柄の同僚や、普段からメールでのやり取りが多い相手に限られます。
役員や社長、重要な取引先の重役など、目上の方に対して、いきなりメールでお悔やみを伝えるのは失礼にあたる可能性が高いでしょう。
また、相手から訃報の連絡がメールで届いた場合には、返信する形でメールを送っても問題ありません。
状況をよく見極め、メールを送るべき相手かどうかを慎重に判断することが大切です。
件名と本文の書き方・文例
お悔やみメールを送る際は、件名を見ただけで内容がすぐに分かるように工夫する必要があります。
例えば、「〇〇株式会社〇〇より お悔やみ申し上げます」のように、会社名と氏名、そしてお悔やみの用件であることを明記しましょう。
本文の構成は、電話の場合と基本的には同じです。
- 宛名
- お悔やみの言葉
- 相手を気遣う言葉
- 返信不要の旨を伝える一文
- 署名
本文では、時候の挨拶などは不要です。
すぐに本題に入り、お悔やみの言葉を述べます。
また、忌み言葉を使わない、故人の敬称(「様」など)を正しく使うといった基本的なマナーは電話と同様です。
そして、最も重要なポイントの一つが、メールの最後に「ご多忙と存じますので、ご返信には及びません」といった一文を添えることです。
これは、相手に返信の手間をかけさせないための心遣いであり、お悔やみメールにおける必須のマナーと言えるでしょう。
弔電を手配する際のマナー

通夜や告別式に参列できない場合、お悔やみの気持ちを伝える方法として弔電(ちょうでん)があります。
弔電は、故人への哀悼の意と、ご遺族へのいたわりの気持ちを伝える電報のことです。
ビジネスシーンでも、会社の代表として送るケースが多々あります。
ここでは、弔電を手配する際の基本的なマナーについて解説します。
弔電を送るタイミング
弔電は、通夜や告別式で読み上げられることが多いため、それに間に合うように手配する必要があります。
理想的なタイミングは、通夜が始まる前までに斎場に届くようにすることです。
訃報を受けたら、できるだけ速やかに手配を始めましょう。
遅くとも、告別式の開始前までには届くように手配しなければなりません。
もし、告別式にも間に合わない場合は、弔電は送らずに、後日、ご遺族のご自宅宛にお悔やみの手紙を送る方が丁寧な対応となります。
宛名と差出人の書き方
弔電の宛名は、喪主(もしゅ)の氏名にするのが一般的です。
もし喪主の名前が分からない場合は、「〇〇様 ご遺族様」としても問題ありません。
送付先は、通夜や告別式が行われる斎場やご自宅の住所を指定します。
差出人の名前は、誰からの弔電かご遺族がすぐに分かるように、正式名称で記載します。
ビジネスで送る場合は、「〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇」のように、会社名、役職、氏名をフルネームで記します。
部署として送る場合は、「〇〇株式会社 営業部一同」とすることもあります。
差出人と故人との関係が、ご遺族に分かりにくいと思われる場合は、氏名の横に「(〇〇の取引先の〇〇です)」のように書き添えると親切です。
香典や供花の相談を受けた場合
お悔やみの気持ちを示す方法として、香典(こうでん)や供花(きょうか・くげ)があります。
特にビジネスシーンでは、会社として供花を贈ることも少なくありません。
ここでは、香典や供花に関する基本的な知識と、特に供花として胡蝶蘭が選ばれる理由について触れていきます。
香典と供花、それぞれの意味
香典とは、故人の霊前に供える金品のことを指します。
元々は、お香やお花の代わりに供えられていたもので、現在では葬儀費用の足しにしてもらうといった相互扶助の意味合いも含まれています。
一方、供花は、故人の霊を慰め、祭壇や会場を飾るために贈るお花のことです。
親族や故人と親しかった友人、そして会社関係から贈られることが一般的です。
近年では、ご遺族の意向により、香典を辞退されるケースも増えています。
その場合は、無理にお渡しせず、供花や弔電でお悔やみの気持ちを伝えるのが良いでしょう。
香典や供花を受け付けているかどうかは、お悔やみの電話をかける際に、失礼にならない範囲で確認することをおすすめします。
供花に胡蝶蘭が選ばれる理由
ビジネスシーンを含め、お悔やみの供花として「胡蝶蘭(こちょうらん)」が選ばれることが非常に多いのをご存知でしょうか。
それには、いくつかの理由があります。
- 品格と清廉さ
- 花粉や香りが少ない
- 日持ちが良い
- 宗教を問わない
まず、胡蝶蘭の佇まいは非常に品格があり、厳粛な場にふさわしいとされています。
特に白色の胡蝶蘭は、清らかで故人を偲ぶ気持ちを表すのに最適です。
また、胡蝶蘭は花粉がほとんどなく、香りも強くないため、斎場やご遺族、他の参列者の迷惑になりにくいという実用的なメリットもあります。
さらに、他の切り花に比べて日持ちが良く、葬儀後も長く飾っていただける点も喜ばれる理由の一つです。
宗教による花の決まり事も特にないため、どのようなお悔やみの場にも安心して贈ることができます。
急な訃報で供花を手配する必要が生じた場合でも、信頼できる通販サイトを利用すれば、高品質な胡蝶蘭を迅速に手配することが可能です。
冠婚葬祭の贈り物として最適な胡蝶蘭は、お悔やみの気持ちを最も格調高く伝えてくれる選択肢の一つと言えるでしょう。
お悔やみ 電話 ビジネスの総まとめ

これまで、お悔やみ 電話 ビジネスにおける様々なマナーや注意点について解説してきました。
突然の訃報に際して、冷静かつ適切に対応するためには、これらの知識を事前にインプットしておくことが何よりも大切です。
最後に、本記事で解説した内容の要点を改めて整理し、おさらいしておきましょう。
お悔やみの電話で最も重要なのは、故人を悼む気持ちと、ご遺族を気遣う心です。
マナーや形式ももちろん大切ですが、その根底にあるべきなのは、相手の悲しみに寄り添う姿勢に他なりません。
言葉遣いは丁寧に、話は簡潔に、そして相手の状況を最大限に配慮することを常に忘れないでください。
また、電話だけでなく、メールや弔電、供花といった様々な方法を状況に応じて使い分けることで、よりきめ細やかなお悔やみの気持ちを伝えることができます。
特に、品格のある胡蝶蘭などの供花は、言葉以上に深い哀悼の意を示してくれるでしょう。
いざという時に、社会人として恥ずかしくない、心のこもった対応ができるよう、この記事の内容をぜひ参考にしてください。
fa-file-powerpoint-o
この記事のまとめ
- ビジネスのお悔やみ電話はマナーを最優先する
- 訃報を受けたらなるべく早く日中に電話をかける
- 深夜早朝や食事時の連絡は絶対に避ける
- 相手別に言葉遣いや伝える内容を調整する
- 長電話は厳禁で要件は簡潔に伝える
- 「重ね重ね」などの忌み言葉は使わない
- 死因などデリケートな内容は自分から尋ねない
- 電話が繋がらなければメールや弔電も検討する
- お悔やみメールでは返信不要の旨を必ず記載する
- 弔電は通夜の開始前までに届くように手配する
- 弔電の宛名は喪主にするのが基本
- 香典や供花は相手の意向を確認してから手配する
- 供花を贈る際は品格のある胡蝶蘭が最適
- 胡蝶蘭は花粉や香りが少なく日持ちも良い
- 信頼できる通販サイトで供花をスムーズに手配できる









