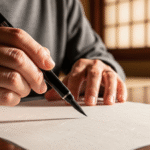親しい友人や大切な身内が家を建てるという知らせは、自分のことのように嬉しいものですね。
しかし、そのお祝いの段階で「上棟祝い」と「新築祝い」という二つの言葉を耳にし、その違いや両方贈るべきなのか、どのようなマナーがあるのか分からず、戸惑ってしまう方も少なくありません。
特に、贈るタイミングや金額の相場、さらにはどのような贈り物が喜ばれるのか、考え始めると次から次へと疑問が湧いてくることでしょう。
また、お祝いの気持ちをしっかりと伝えるための「のし」の選び方やメッセージの書き方、そしてお返しは必要なのかといった点も気になるところです。
家を建てるという人生の大きな節目に際して、相手に心から喜んでもらえるような、心のこもったお祝いをしたいものです。
そのためには、上棟祝い 新築祝いのそれぞれの意味を正しく理解し、適切なマナーを守ることが何よりも大切になります。
このようにお祝いの場面で失敗しないためにも、しっかりとした知識を身につけておきたいと考えるのは当然のことです。
この記事では、そんなあなたの悩みを解決するために、上棟祝いと新築祝いの基本的な違いから、具体的なマナー、金額の相場、贈り物の選び方まで、網羅的に詳しく解説していきます。
fa-hand-pointer-o
この記事で分かる事、ポイント
- 上棟祝いと新築祝いの明確な違い
- それぞれのお祝いを贈る最適なタイミング
- 贈る相手との関係性に応じた金額の相場
- 両方のお祝いを贈るべきかどうかの判断基準
- 喜ばれる贈り物の選び方と避けるべき品物
- 正しい「のし」の選び方や表書きの書き方
- お祝いに対するお返しの必要性やマナー
◆ココに広告貼り付け◆
上棟祝い 新築祝いの基本的な違いとマナー
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- そもそも上棟祝いと新築祝いの違いとは
- 贈るタイミングはいつが最適か
- 関係性で見るお祝いの金額相場
- 上棟祝いと新築祝いは両方贈るべき?
- 身内へのお祝いはどうすれば良いか
家づくりにおける大きなお祝いとして、上棟祝いと新築祝いが存在します。
これらは似ているようで、その意味合いや対象、タイミングが全く異なるものです。
祝福の気持ちを正しく伝えるためには、まずこの二つの違いを明確に理解しておくことが重要です。
この章では、上棟祝い 新築祝いの基本的な知識として、それぞれの違い、贈るのに最適な時期、関係性ごとに変わる金額の相場、そして両方贈る必要があるのかどうかといった、多くの人が抱える疑問について詳しく解説していきます。
特に身内のような近しい間柄の場合、どのようにお祝いをすれば良いのか迷うことも多いため、具体的なポイントを交えながら説明を進めていきます。
これらの基本をしっかりと押さえることで、相手に失礼なく、心からのお祝いの気持ちを伝えることができるようになるでしょう。
そもそも上棟祝いと新築祝いの違いとは

上棟祝いと新築祝いは、どちらも家の完成を祝うものですが、その目的と贈る相手が大きく異なります。
この違いを理解することが、正しいマナーでお祝いをするための第一歩となります。
まず、上棟祝いについて説明します。
これは、建物の骨組みが完成し、最上部に棟木(むなぎ)と呼ばれる木材を取り付ける「上棟式(じょうとうしき)」または「棟上げ(むねあげ)」の際に行われるお祝いです。
このお祝いの主な目的は、工事の無事を感謝し、今後の工事の安全を祈願することにあります。
そして、お祝いを贈る主な対象は、施主(家を建てる人)ではなく、工事を担う棟梁や大工さん、工事関係者です。
施主から工事関係者への感謝と労いの気持ちを示す意味合いが強いのが特徴です。
一方で、新築祝いは、建物がすべて完成し、人が住める状態になってから贈るお祝いです。
こちらは、無事に家が完成したこと、そして新しい生活が始まることを祝福するものです。
したがって、お祝いを贈る対象は、その家に住むことになる施主やその家族となります。
友人や親戚、同僚など、施主と親しい間柄の人が贈るのが一般的です。
この二つの違いを分かりやすく表にまとめてみましょう。
| 項目 | 上棟祝い | 新築祝い |
|---|---|---|
| 目的 | 工事の安全祈願と工事関係者への感謝・労い | 家の完成と新しい生活の始まりを祝福 |
| 贈るタイミング | 上棟式(棟上げ)当日 | 建物完成後、入居してから1〜2ヶ月以内 |
| 贈る相手 | 棟梁、大工、工事関係者 | 施主(家の持ち主)とその家族 |
| 贈り物の内容 | ご祝儀(現金)、お酒、ビール、お弁当、手土産など | 現金、商品券、家電、インテリア雑貨、カタログギフトなど |
このように、上棟祝いは「工事の過程」に対するお祝いであり、新築祝いは「家の完成と新生活」に対するお祝いであると考えると、その違いが明確になります。
自分がどちらの立場で、誰に対してお祝いをしたいのかを考えることで、どちらの贈り物を準備すれば良いのかが判断できるでしょう。
親しい間柄であれば両方に関わることもありますが、一般的には友人や知人としてお祝いする場合は新築祝いを贈ることがほとんどです。
贈るタイミングはいつが最適か
お祝いを贈るタイミングは、相手への配慮を示す上で非常に重要なマナーの一つです。
早すぎても遅すぎても失礼にあたる可能性があるため、それぞれのお祝いに最適な時期を把握しておきましょう。
上棟祝いを贈るタイミング
上棟祝いは、前述の通り「上棟式」の当日に贈るのが基本です。
上棟式は、工事の安全を祈願する神事であり、工事関係者が集まる日です。
そのため、施主が工事関係者へご祝儀や手土産を渡すのに最も適した日と言えます。
もし施主の親族としてお祝いを持参する場合も、式の開始前に施主に直接手渡すのが良いでしょう。
これにより、施主が工事関係者へ配る分と合わせてスムーズに渡すことができます。
もし上棟式に出席できない場合は、式の前日までに届くように手配するのがマナーです。
当日は施主も準備で忙しくしていることが多いため、前もって渡しておくことで相手の負担を軽減できます。
最近では、上棟式自体を簡略化したり、行わなかったりするケースも増えています。
その場合は、施主に直接意向を確認し、「上棟御祝」として現金などを事前に渡すのが丁寧な対応です。
新築祝いを贈るタイミング
新築祝いを贈るタイミングは、相手が新しい家に移り住み、生活が少し落ち着いてからが最適です。
具体的には、入居後から1ヶ月後、遅くとも2ヶ月以内が目安とされています。
引越し直後は、荷解きや手続きなどで非常に忙しく、来客対応が難しいことが多いものです。
そのため、相手の都合を考えずに入居後すぐに訪問するのは避けるべきです。
お祝いを贈る前に、まずは相手に連絡を取り、都合の良い日時を確認しましょう。
新居のお披露目会(ハウスウォーミングパーティー)に招待された場合は、その際に持参するのが最もスマートです。
お披露目会がない場合や、遠方で直接訪問が難しい場合は、配送を利用するのも一つの方法です。
その際も、相手が受け取りやすい日時を事前に確認してから発送する心遣いが大切です。
贈り物が早すぎると、まだ収納場所が片付いていない新居で置き場所に困らせてしまう可能性があります。
逆に、入居から半年以上経過するなど、タイミングを逃してしまった場合は、「新築祝い」としてではなく、別の名目、例えば「お引越し祝い」や、季節の挨拶に合わせて「御中元」「御歳暮」として贈るなどの配慮も考えると良いでしょう。
いずれのお祝いも、相手の状況を最優先に考え、最適なタイミングを見計らうことが、祝福の気持ちを伝える上で最も大切なことと言えます。
関係性で見るお祝いの金額相場

上棟祝いや新築祝いを贈る際に、最も悩むのが「いくら包めば良いのか」という金額の問題ではないでしょうか。
金額が少なすぎると失礼にあたるかもしれませんし、多すぎるとかえって相手に気を使わせてしまう可能性があります。
お祝いの金額は、贈る相手との関係性の深さによって大きく変わるのが一般的です。
ここでは、関係性別の金額相場を具体的に見ていきましょう。
上棟祝いの金額相場
上棟祝いは、主に施主が工事関係者へ渡すものですが、親族が施主へお祝いとして渡すケースもあります。
- 親・兄弟・親戚から施主へ: 10,000円~30,000円程度。ご祝儀の他に、工事関係者への差し入れ用のお酒やビールなどを贈ることもあります。
- 施主から工事関係者へ:
- 棟梁: 10,000円~30,000円
- その他の大工・職人: 3,000円~5,000円
これはあくまで一般的な相場です。
地域の慣習やハウスメーカーの方針によっても異なるため、事前に確認しておくと安心です。
最近では、安全管理上の理由から、現場での現金の受け取りを辞退するケースもあります。
その場合は、感謝の気持ちとして個包装のお菓子や飲み物などの手土産を用意するのが良いでしょう。
新築祝いの金額相場
新築祝いは、贈る相手との関係性によって相場がより細かく分かれます。
| 贈る相手 | 金額の相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 親 | 50,000円~100,000円 | 現金でなく、高価な家電や家具を贈ることも多い。 |
| 兄弟・姉妹 | 30,000円~50,000円 | 兄弟間で相談して金額を合わせるのが一般的。 |
| その他の親戚 | 10,000円~30,000円 | 普段のお付き合いの深さに応じて調整する。 |
| 友人・知人 | 5,000円~10,000円 | 複数人で連名にして、少し高価な品物を贈るのもおすすめ。 |
| 職場の上司 | 5,000円~10,000円 | 現金は失礼にあたる場合があるため、品物で贈るのが無難。 |
| 職場の同僚・部下 | 3,000円~5,000円 | 部署内で連名にするケースが多い。一人当たりの負担は1,000円~3,000円程度。 |
これらの金額はあくまで目安です。
過去に自分がお祝いをいただいた経験がある場合は、その時の金額を参考にするのが良いでしょう。
また、「死」や「苦」を連想させる4や9のつく金額は避けるのがマナーです。
お祝い金の相場は、気持ちを表す一つの尺度に過ぎません。
最も大切なのは、相手の新しい門出を祝う心です。
相場を参考にしつつも、無理のない範囲で、自分の気持ちに合った金額や品物を選ぶことが重要です。
上棟祝いと新築祝いは両方贈るべき?
家づくりのお祝いにおいて、「上棟祝いと新築祝い、両方を贈るべきなのか」という点は、多くの人が迷うポイントです。
結論から言うと、必ずしも両方を贈る必要はありません。
どちらか一方、あるいは両方を贈るかは、施主との関係性によって判断するのが一般的です。
一般的な友人・知人・同僚の場合
友人や会社の同僚といった一般的な関係性であれば、「新築祝い」のみを贈るのが通常です。
前述の通り、上棟祝いは本来、工事関係者への労いを目的とするものです。
そのため、施主の友人や知人が上棟式に参加したり、上棟祝いを贈ったりするケースは稀です。
家が完成し、新生活がスタートしたタイミングで、心のこもった新築祝いを贈ることで、十分にお祝いの気持ちは伝わります。
もし上棟式に招待されたなど、特別な事情がある場合は、施主に直接相談してみるのが良いでしょう。
その場合でも、大掛かりなお祝いではなく、手土産程度のお菓子や飲み物を持参するのがスマートです。
親・兄弟など近しい身内の場合
一方で、施主が自分の子どもや兄弟であるなど、非常に近しい身内の場合は、話が少し変わってきます。
この場合、上棟祝いと新築祝いの両方を贈ることも珍しくありません。
家を建てるということは、本人たちにとって非常に大きな一大事業です。
その過程の節目である上棟式と、完成の節目である新築祝い、その両方でお祝いの気持ちを表したいと考えるのは自然なことです。
両方を贈る場合の考え方としては、以下のようなパターンが考えられます。
- 両方ともしっかりお祝いする:上棟祝いとしてご祝儀を包み、さらに新築祝いとして現金や品物を贈る。親から子へのお祝いなど、援助の意味合いも含む場合に多く見られます。
- お祝いを分割して贈る:新築祝いとして予定していた金額の一部を、前倒しで上棟祝いとして渡し、残りを新築祝いとして贈るパターンです。
- 役割を分担して贈る:上棟祝いでは工事関係者への差し入れ(お酒やビールなど)を担当し、新築祝いでは現金や希望の品物を贈るという方法です。
ただし、これも家庭や地域の考え方によって様々です。
「お祝いは一度にまとめて渡したい」という考え方もあります。
身内だからこそ、率直に「お祝いはどうしたら良い?」と本人に直接聞いてみるのが最も確実で、相手にとっても喜ばれる方法かもしれません。
相手の意向を確認しながら、自分たちの気持ちに合った形でお祝いをするのが一番です。
身内へのお祝いはどうすれば良いか

自分の子どもや兄弟、親戚など、身内が家を建てる際のお祝いは、友人や知人へのお祝いとは少し異なる配慮が必要になることがあります。
金額の相場が高くなる傾向があるだけでなく、より心のこもった、そして実用的なサポートが喜ばれることも多いでしょう。
金額や贈り物の考え方
まず金額については、前述の通り、親から子へは5万円~10万円、兄弟姉妹間では3万円~5万円が一般的な相場とされています。
しかし、これはあくまで目安です。
各家庭の経済状況や、これまでの親戚付き合いの慣習によっても変わってきます。
例えば、兄弟姉妹間でお祝いを贈る場合は、事前に相談して金額を揃えておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。
誰か一人が突出して高額だったり、逆に少なかったりすると、お互いに気まずい思いをしてしまう可能性があるからです。
また、現金で渡すだけでなく、新生活に必要なものをプレゼントする「品物」でのお祝いも非常に喜ばれます。
その際は、本人たちに直接「何か欲しいものはない?」とリクエストを聞くのが一番です。
新しい家に合わせて家具や家電を新調したいと考えていることも多く、高価なものであれば親や兄弟で費用を分担して購入するという方法もあります。
自分たちではなかなか手が出せない少しグレードの高い家電や、デザイン性の高い家具などは、お祝いの品として最適です。
上棟式への関わり方
身内であれば、上棟式に呼ばれることもあります。
その際は、施主である家族をサポートする気持ちで参加すると良いでしょう。
例えば、上棟祝いとして現金を包むだけでなく、工事関係者の方々への差し入れとして、飲み物やお弁当、お菓子などを手配する手伝いをするのも喜ばれます。
当日は施主も何かと忙しくしているため、「差し入れは任せてね」と声をかけるだけでも、大きな助けになるはずです。
地域の風習に詳しい親戚がいる場合は、どのような準備が必要かアドバイスを求めるのも良い方法です。
心遣いが何よりも大切
最終的に、身内へのお祝いで最も大切なのは、金額や品物の価値だけではありません。
家づくりという大変なプロジェクトを無事に終えたことへの労いと、新しい生活のスタートを心から祝福する気持ちです。
「何か手伝えることがあったら、いつでも声をかけてね」という一言や、引越しの手伝いを申し出るなどの心遣いが、何よりも嬉しい贈り物になることもあります。
形式的なマナーも大切ですが、身内だからこそできる温かいサポートを心がけることで、より一層お祝いの気持ちが伝わるでしょう。
上棟祝い 新築祝いに喜ばれる贈り物の選び方
fa-ellipsis-v
この章のポイント
- おすすめの贈り物と避けるべき品物
- ご祝儀袋の「のし」に関する正しい知識
- 気持ちが伝わるお祝いメッセージの文例
- お祝いへのお返しは必要?相場と品物
- 知っておきたい贈る際のマナー
- まとめ:上棟祝い 新築祝いはマナーを守り祝福を伝えよう
お祝いの気持ちを形にする贈り物は、相手のことを考えて選ぶ時間が楽しいものである一方、何を贈れば本当に喜んでもらえるのか、頭を悩ませるものでもあります。
特に上棟祝い 新築祝いでは、それぞれに適した品物や、逆に避けるべきとされる品物が存在します。
また、現金を贈る際のご祝儀袋の選び方や書き方、心からの祝福を伝えるメッセージの文例など、贈り物にまつわるマナーは多岐にわたります。
この章では、相手の笑顔を思い浮かべながら、自信を持って贈り物を選べるように、具体的なおすすめの品や避けるべきアイテム、そしてご祝儀袋やメッセージに関する正しい知識を詳しく解説します。
さらには、お祝いをいただいた側が考える「お返し」の必要性やマナーについても触れていきます。
これらのポイントを押さえることで、あなたの祝福の気持ちがより深く、そして正しく相手に伝わるはずです。
おすすめの贈り物と避けるべき品物

贈り物は、相手の好みやライフスタイルを考慮して選ぶことが大前提ですが、お祝い事には古くからの慣習や縁起担ぎがあり、それに沿った品物選びも大切です。
ここでは、上棟祝いと新築祝い、それぞれにおすすめの贈り物と、マナーとして避けた方が良い品物をご紹介します。
上棟祝いにおすすめの贈り物
上棟祝いは工事関係者への労いが主な目的のため、その場で皆で分け合えるものや、疲れを癒すものが喜ばれます。
- お酒・ビール:「祝上棟」などの熨斗をつけた日本酒やビールのケースは定番です。工事関係者の好みが分からない場合は、複数の種類が入った詰め合わせも良いでしょう。
- ご祝儀(現金):施主から工事関係者へ渡す場合、最も実用的で喜ばれることが多いです。親族が施主へ贈る場合も、何かと物入りな時期の助けになります。
- お弁当や仕出し:上棟式後、簡単な宴会(直会)を行う場合に、その食事を差し入れとして提供する形です。施主と事前に相談が必要です。
- お菓子や飲み物の詰め合わせ:休憩時間に皆でつまめる個包装のお菓子や、ペットボトルのお茶やジュースなども実用的で歓迎されます。
新築祝いにおすすめの贈り物
新築祝いは、新しい生活を彩るアイテムや、実用的なものが人気です。
- 現金・商品券:何かと出費がかさむ時期なので、好きなものを購入できる現金や商品券は、やはり最も喜ばれる贈り物の一つです。
- カタログギフト:相手に好きなものを選んでもらえるため、好みや他の人からの贈り物と重複する心配がなく、近年非常に人気があります。
- 観葉植物:新しい家のインテリアに彩りを添えてくれます。「根付く」という意味合いから、縁起が良いとされています。お手入れが簡単な種類を選ぶと良いでしょう。
- おしゃれな家電:コーヒーメーカーや電気ケトル、ホットプレートなど、デザイン性の高いキッチン家電は新生活を豊かにしてくれます。
- タオルや洗剤などの消耗品:上質なタオルセットや、自分では買わないような少し高級な洗剤セットは、いくつあっても困らない実用的なギフトです。
- 時計:「新しい時を刻む」という意味で、掛け時計や置き時計も縁起の良い贈り物とされています。
避けるべき品物
一方で、新築祝いでは縁起が悪いとされるため、避けるべき品物があります。
火事を連상させるものは、新築祝いのタブーとされています。
- ライター、灰皿、アロマキャンドル、コンロなど:これらは直接的に火を扱うため、絶対に避けるべきです。
- 赤い色のもの:赤い花束や赤いインテリア雑貨なども、炎を連想させるため避けた方が無難とされています。
- 壁に穴を開ける必要があるもの:絵画や壁掛け時計などは喜ばれる品ですが、相手が壁に傷をつけたくないと考えている可能性もあります。贈る場合は、事前に確認するのが賢明です。
- スリッパやマット類:これらは「踏みつける」という意味合いにつながるため、特に目上の方へ贈るのは失礼にあたるとされています。
最も大切なのは、相手の気持ちを考えることです。
もし相手から具体的にリクエストがあった場合は、これらのタブーに当てはまるものでも贈って問題ありません。
相手の好みが分からない場合や、マナーに不安がある場合は、カタログギフトや商品券を選ぶのが最も安心な選択と言えるでしょう。
ご祝儀袋の「のし」に関する正しい知識
現金を贈る際に使用するご祝儀袋。
その選び方や書き方にも、お祝いの気持ちを正しく伝えるための大切なマナーがあります。
特に、水引(みずひき)や表書き(おもてがき)は、間違えやすいポイントなのでしっかりと確認しておきましょう。
水引の選び方
水引とは、ご祝儀袋の中央にかけられている飾り紐のことです。
結び方や色にそれぞれ意味があり、用途によって使い分ける必要があります。
上棟祝いや新築祝いのような、何度あっても嬉しいお祝い事には、「紅白の蝶結び(花結び)」の水引を選びます。
蝶結びは、何度も結び直せることから、「繰り返したいお祝い」に使われます。
結婚祝いなどで使われる「結び切り」や「あわじ結び」は、一度結ぶと解くのが難しいことから、「一度きりであってほしいお祝い」に使われるものです。
新築祝いにこれらを選んでしまうと、大変失礼にあたるため注意が必要です。
表書きの書き方
表書きは、水引の上段中央に書くお祝いの名目のことです。
毛筆や筆ペンを使い、楷書で丁寧に書きましょう。
- 上棟祝いの場合: 「祝上棟」「御上棟御祝」「上棟式御祝」など
- 新築祝いの場合: 「祝御新築」「御新築御祝」「新築御祝」など
マンション購入の場合は「御新居御祝」、中古住宅の購入やリフォームの場合は「御引越御祝」などと使い分けると、より丁寧な印象になります。
名前の書き方
水引の下段中央には、贈り主の氏名をフルネームで書きます。
表書きよりも少し小さめの文字で書くとバランスが良く見えます。
- 個人の場合:中央に氏名を書きます。
- 夫婦連名の場合:中央に夫の氏名を書き、その左側に妻の名前のみを書きます。
- 3名までの連名の場合:役職や年齢が上の人を一番右に書き、そこから左へ順に名前を並べます。友人同士など同格の場合は、五十音順で書くのが一般的です。
- 4名以上の場合:代表者の氏名を中央に書き、その左側に「外一同(他一同)」と書き添えます。そして、全員の氏名を書いた紙を中袋に同封します。職場などで贈る場合は、代表者の氏名の代わりに「〇〇部一同」とすることもあります。
中袋(中包み)の書き方
お札を入れる中袋にも、書くべき項目があります。
表面の中央には、包んだ金額を「金〇萬圓」というように、大字(だいじ)で書くのが正式なマナーです。
(例:壱、弐、参、伍、萬)
ただし、最近では算用数字で「金〇〇,〇〇〇円」と書いても問題ないとされています。
裏面の左下には、贈り主の住所と氏名を書きます。
これは、相手がお返し(内祝い)の準備をする際に必要となる情報ですので、忘れずに記入しましょう。
お札を入れる向きは、お札の表面(肖像画が描かれている方)が中袋の表側に来るようにし、さらに肖像画が上に来るように揃えて入れます。
新札を用意するのが望ましいですが、難しい場合はできるだけ綺麗なお札を選びましょう。
気持ちが伝わるお祝いメッセージの文例

贈り物に手書きのメッセージを添えることで、お祝いの気持ちがより一層深く伝わります。
しかし、いざ書こうとすると、どのような言葉を選べば良いか悩んでしまうこともあるでしょう。
ここでは、さまざまなシチュエーションで使えるメッセージの文例をいくつかご紹介します。
メッセージを書く際のポイントは、お祝いの言葉と共に、相手の努力を労う気持ちや、新しい生活への期待を込めることです。
また、新築祝いのメッセージでは、「燃える」「焼ける」「倒れる」「崩れる」といった火事や倒壊を連想させる忌み言葉は使わないように気をつけましょう。
友人・知人へのメッセージ文例
親しい間柄の友人には、少しくだけた表現を交えつつ、温かい気持ちを伝えるのが良いでしょう。
- 文例1:「〇〇さん、マイホームの完成、本当におめでとう!こだわりの詰まった素敵なおうち、遊びに行くのが今からとても楽しみです。新しいおうちで、家族みんなが笑顔で過ごせますように。ささやかですが、お祝いの品を贈ります。ぜひ新生活で役立ててくださいね。」
- 文例2:「ご新築おめでとうございます!ついに夢のマイホームだね!家づくり、本当にお疲れ様でした。これからは新しいおうちで、〇〇さんらしい素敵な家庭を築いていってください。また落ち着いたら、ぜひ新居にお邪魔させてね!」
職場の上司や目上の方へのメッセージ文例
目上の方へは、丁寧な言葉遣いを心がけ、敬意を表すことが大切です。
- 文例1:「この度は、ご新築誠におめでとうございます。素晴らしいお住まいが完成されましたこと、心よりお慶び申し上げます。ご家族の皆様の新しい門出が、幸多きものとなりますようお祈りしております。お祝いのしるしまでに、心ばかりの品をお贈りいたしました。どうぞご笑納ください。」
- 文例2:「〇〇様 この度は、立派なご新居の完成、誠におめでとうございます。ご家族皆様の長年の夢が叶いましたこと、私まで嬉しく感じております。皆様の新しい生活が、ますますご発展されますことを心より祈念いたします。」
親戚や兄弟へのメッセージ文例
身内へは、祝福の気持ちに加えて、これまでの頑張りを労う言葉や、今後の幸せを願う気持ちをストレートに伝えると良いでしょう。
- 文例1:「新築おめでとう!そして、家づくり本当にお疲れ様でした。素敵な家が完成して、私たちも本当に嬉しいです。これからはこの新しい家で、たくさんの楽しい思い出を作っていってね。何か手伝えることがあったら、いつでも遠慮なく声をかけてください。」
- 文例2:「待望のマイホーム完成、おめでとう!〇〇(名前)のこだわりがたくさん詰まった、本当に素敵なおうちだね。ご家族の笑顔が目に浮かびます。新しい家での生活が、幸せいっぱいの毎日になることを心から願っています。」
これらの文例を参考に、自分自身の言葉で、相手との関係性や思い出を交えながらメッセージを作成することで、より心のこもった、世界に一つだけのお祝いの言葉になるでしょう。
お祝いへのお返しは必要?相場と品物
上棟祝いや新築祝いをいただいた側になったとき、次に考えるのが「お返し」についてです。
お祝いに対するお返しは「内祝い(うちいわい)」と呼ばれ、感謝の気持ちを伝えるための大切な習慣です。
お返しの必要性
まず、上棟祝いへのお返しは、基本的に不要とされています。
上棟祝いは、施主が工事関係者へ渡す労いの意味合いが強いものです。
もし親族などから施主へ「上棟御祝」をいただいた場合は、新築祝いをいただいた際のお返しとまとめて「新築内祝い」として贈るのが一般的です。上棟式の際に、その場で引き出物のような形でお返しを渡す地域もあります。
一方で、新築祝いをいただいたら、お返し(新築内祝い)をするのがマナーです。
高価な品物や現金をいただいた場合はもちろん、少額のプレゼントや、お披露目会に手土産を持参してくれた方へもお返しを用意するのが丁寧な対応です。
ただし、会社の福利厚生としていただいたお祝い金や、「一同」としていただいたお祝いなど、お返しが不要とされているケースもあります。
お返しの金額相場とタイミング
内祝いの金額相場は、いただいたお祝いの品物や現金の「3分の1から半額(半返し)」が目安です。
例えば、10,000円のお祝いをいただいたら、3,000円~5,000円程度の品物をお返しとして選びます。
いただいた品物の金額が分からない場合は、インターネットなどでおおよその値段を調べて参考にすると良いでしょう。
お返しを贈るタイミングは、お祝いをいただいてから1~2ヶ月以内が目安です。
新居のお披露目会を開く場合は、その際にお土産として手渡しするのが最もスマートです。
お披露目会に来られなかった方や、配送でお祝いをいただいた方へは、時期を逃さないように内祝いの品を発送しましょう。
内祝いにおすすめの品物
内祝いの品は、相手に気を使わせない程度の「消えもの」が人気です。
- お菓子の詰め合わせ
- コーヒーや紅茶のセット
- タオルや石鹸などの日用品
- 調味料のセット
- 入浴剤
相手の好みに合わせて選べるカタログギフトも、内祝いとして定番の品です。
内祝いの品には、新築祝いと同様に「紅白の蝶結び」ののし紙をかけ、表書きは「新築内祝」または「内祝」とし、下段には世帯主の姓、または家族の連名を記載します。
その際、新しい家の写真や、家族の写真を添えたお礼状を同封すると、感謝の気持ちがより伝わりやすくなります。
知っておきたい贈る際のマナー

お祝いの気持ちを台無しにしてしまわないためにも、贈り物を渡す際の基本的なマナーはしっかりと押さえておきたいものです。
ここでは、特に新築祝いを直接手渡しする際の注意点について解説します。
訪問前のアポイントメント
新築の家へお祝いを持って訪問する際は、必ず事前に相手の都合を確認し、アポイントメントを取りましょう。
「近くまで来たから」といって、突然訪問するのはマナー違反です。
前述の通り、引越し前後は非常に忙しく、家の中も片付いていないことが多いものです。
相手が快く迎えられるよう、訪問日時を約束してから伺うのが鉄則です。
訪問時間は、食事時を避け、長居しすぎないように配慮することも大切です。
1~2時間程度で切り上げるのがスマートな大人の対応と言えるでしょう。
贈り物を渡すタイミング
家に招き入れられたら、まずはお祝いの言葉を述べます。
贈り物を渡すタイミングは、玄関先ではなく、部屋に通されて挨拶が済んだ後が一般的です。
紙袋や風呂敷から品物を取り出し、相手に正面を向けて両手で丁寧に手渡します。
その際、「ささやかですが、お祝いの気持ちです」「皆さんで召し上がってください」など、一言添えるとより気持ちが伝わります。
贈り物を入れた紙袋は、相手に渡さず、自分で持ち帰るのが正式なマナーです。
服装や手土産について
新居のお披露目会に招待された際の服装は、カジュアルすぎず、フォーマルすぎない「スマートカジュアル」程度が適しています。
清潔感のある服装を心がけましょう。
新築祝いの品とは別に、皆でその場で楽しめるようなお菓子や飲み物などを「手土産」として持参すると、ホストである相手への心遣いが伝わり、喜ばれます。
ケーキやフルーツ、少し珍しいお惣菜などがおすすめです。
家のことを褒める
家は、持ち主にとってこだわりや想いが詰まった特別な空間です。
家の中を案内してもらったら、具体的なポイントを挙げて褒めるようにしましょう。
「日当たりが良くて明るいリビングですね」「この壁紙、とてもおしゃれですね」など、具体的に褒めることで、相手は「よく見てくれている」と嬉しい気持ちになります。
ただし、収納の中を勝手に開けたり、寝室などのプライベートな空間にズカズカと入り込んだりするのは厳禁です。
あくまで案内された範囲を見学するようにしましょう。
これらのマナーは、相手を敬い、思いやる気持ちの表れです。
基本的なマナーを守ることで、お互いに気持ちの良い時間を過ごすことができ、祝福の気持ちもまっすぐに伝わるはずです。
まとめ:上棟祝い 新築祝いはマナーを守り祝福を伝えよう
ここまで、上棟祝い 新築祝いに関する様々な情報をご紹介してきました。
二つのお祝いの根本的な違いから、贈るタイミング、金額の相場、そして贈り物にまつわる細かなマナーまで、ご理解いただけたのではないでしょうか。
上棟祝いは、家の骨組みが完成した段階で、主に工事関係者への感謝と労いを伝えるためのお祝いです。
一方で新築祝いは、家が完全に完成し、新しい生活がスタートする施主(家族)に対して贈る祝福の気持ちです。
この基本的な違いを理解することが、すべてのマナーの出発点となります。
友人や知人であれば新築祝いを、親や兄弟といった近しい身内であれば、両方のお祝いに関わることもあるでしょう。
どちらの場合でも、最も大切なのは、相手の状況や気持ちを思いやる心です。
金額の相場やマナーは、あくまで一般的な目安であり、相手との関係性や地域の慣習によっても変化します。
形式にとらわれすぎるのではなく、なぜそのようなマナーがあるのかという背景を理解し、心を込めてお祝いすることが重要です。
この記事で得た知識が、あなたが大切な方の人生の節目に、自信を持って心からの祝福を伝えるための一助となれば幸いです。
正しいマナーを身につけることは、相手への最高の思いやりです。
ぜひ、心のこもった素敵なお祝いを実現してください。
fa-file-powerpoint-o
この記事のまとめ
- 上棟祝いは工事関係者への感謝と安全祈願のお祝い
- 新築祝いは施主への家の完成と新生活を祝うもの
- 上棟祝いは上棟式当日に贈るのが基本
- 新築祝いは入居後1ヶ月から2ヶ月後が最適なタイミング
- お祝いの金額相場は贈る相手との関係性で決まる
- 親族以外は新築祝いのみを贈るのが一般的
- 身内へのお祝いは現金だけでなく品物や援助も喜ばれる
- 新築祝いには火を連想させる赤いものやライターは避ける
- ご祝儀袋の水引は紅白の蝶結びを選ぶ
- 表書きは「祝御新築」など用途に合わせて正しく書く
- メッセージを添えることでよりお祝いの気持ちが伝わる
- 新築祝いをいただいたら半額程度の内祝いをお返しする
- お返し不要なのは上棟祝いや一部の職場でのお祝い
- 新居への訪問は必ず事前にアポイントを取るのがマナー
- 上棟祝い 新築祝いはマナーを守り心からの祝福を伝えることが大切